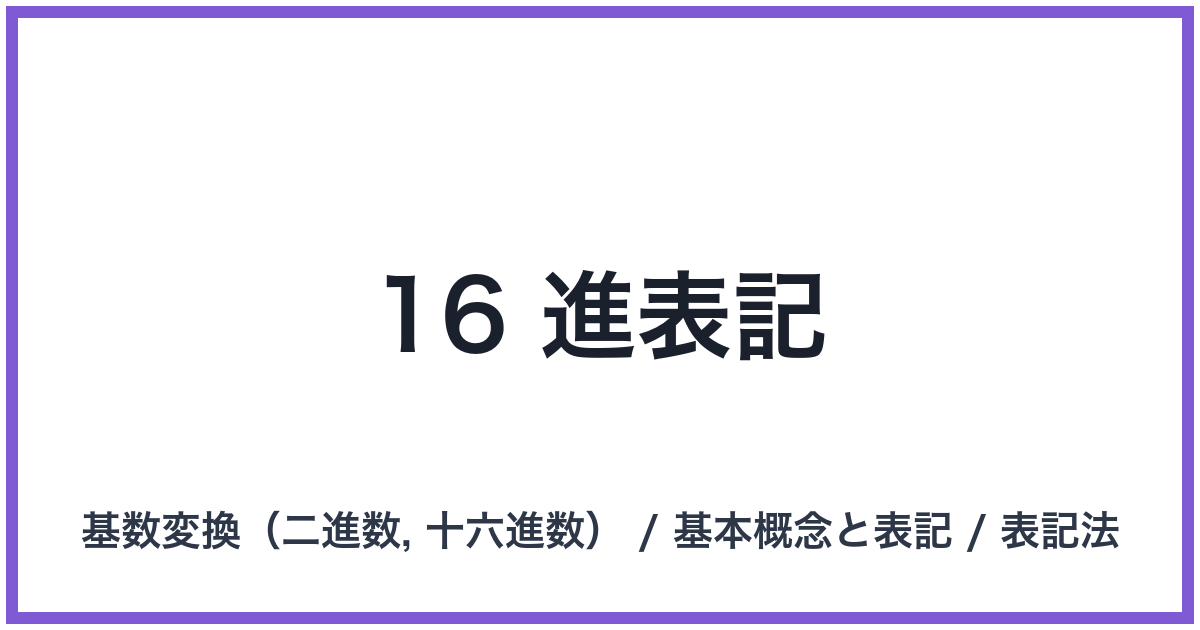16 進表記
英語表記: Hexadecimal Notation
概要
16進表記(じゅうろくしんひょうき)は、デジタル機器が扱う二進数(0と1)の膨大な情報を、人間にとって読みやすく、簡潔に表現するための「表記法」の一つです。私たちが基数変換の分野で学ぶ中でも、特に二進数と密接な関係を持つ重要な概念であり、基数として16を用いて数を表現します。具体的には、0から9の数字と、10から15に対応するAからFのアルファベット、合計16種類の記号を使って数値を構成するのが特徴です。この表記法は、コンピュータ内部のデータを効率的に把握するために欠かせない、基本的な「表記法」として広く利用されています。
詳細解説
階層における位置づけ:表記の効率化
この16進表記は、私たちが学んでいる「基数変換(二進数, 十六進数)→ 基本概念と表記 → 表記法」という道筋において、最も実用的な「表記法」として位置づけられます。その最大の目的は、コンピュータが扱う情報の基本単位である二進数の長大さを解決し、人間が扱えるサイズに圧縮することにあります。
コンピュータの内部では、すべてのデータは「0」と「1」の羅列である二進数で処理されます。例えば、わずか32ビット(4バイト)の情報でも、二進数で表現すると32桁にも及び、これを人間が正確に読み書きしたり、デバッグしたりするのは非常に困難です。
16進表記の仕組みと優位性
ここで16進表記が持つ数学的な性質が大きな力を発揮します。基数16は、基数2の4乗($16 = 2^4$)であるため、二進数のちょうど4桁(4ビット)を、16進数のたった1桁で表現できるという、非常に美しい対応関係が成り立っているのです。
この仕組みにより、二進数の桁数が4分の1に短縮されます。例えば、二進数で表現された8桁の「11010110」という値は、4桁ずつに区切り、「1101」と「0110」に分けられます。「1101」は16進数で「D」に、「0110」は「6」に対応するため、全体としてわずか2桁の「D6」と表現できるのです。
| 10進数 | 16進表記 | 2進数 (4ビット) |
| :—: | :—: | :—: |
| 0 | 0 | 0000 |
| 9 | 9 | 1001 |
| 10 | A | 1010 |
| 15 | F | 1111 |
この