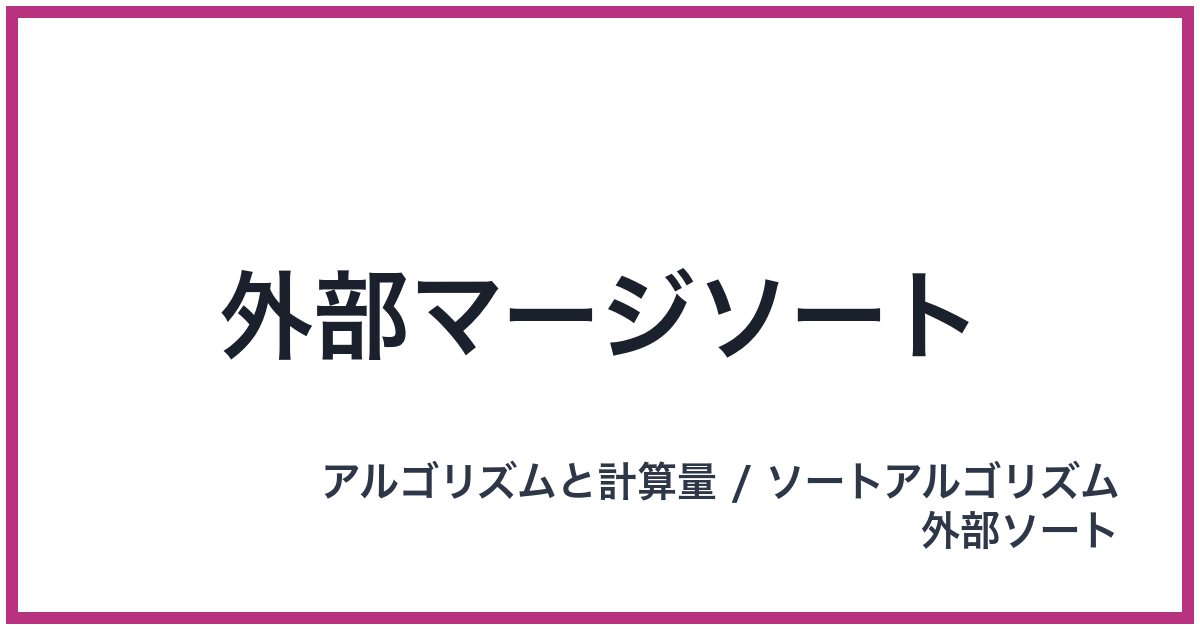外部マージソート
英語表記: External Merge Sort
概要
外部マージソートは、分類上「アルゴリズムと計算量」における「ソートアルゴリズム」の中でも、特に主記憶装置(RAM)に収まりきらないほど巨大なデータセットを効率的に整列するために利用される「外部ソート」の一種です。このアルゴリズムは、効率的な内部ソートとして知られるマージソートの「分割と併合」の考え方を応用しており、大規模データ処理の基盤技術として非常に重要です。データを主記憶の容量に合わせて小分けにし、外部記憶装置(ハードディスクやSSDなど)上でこれらの整列済みブロックを段階的に併合していくことで、メモリ制約を克服し、全体を整列させることを可能にします。
詳細解説
外部マージソートの存在意義は、タキソノミにおける「外部ソート」という位置づけそのものにあります。一般的なソートアルゴリズムは、データ全体がRAMに収まっていることを前提としていますが、現代のビッグデータ時代においては、数テラバイトに及ぶファイルを扱うことが珍しくありません。このような巨大データはRAMに一度にロードできないため、外部記憶装置を主戦場とする外部ソートが必要となるわけです。
外部ソートの目的と課題
外部ソートの最大の目的は、巨大なデータを整列することですが、この際にボトルネックとなるのが、外部記憶装置へのアクセス(I/O操作)です。CPUの処理速度に比べて、ディスクへの読み書きは非常に時間がかかるため、外部ソートの性能は、いかにI/O回数を最小限に抑えるかにかかっています。外部マージソートは、このI/O効率を最大限に高めるために設計されています。
動作の2つの主要フェーズ
外部マージソートは、マージソートの原理に基づき、効率的なI/Oを実現するために以下の二つの明確なフェーズに分けて処理を実行します。
1. 分割(ラン生成)フェーズ
このフェーズでは、まず巨大な入力データを主記憶(RAM)の容量に合わせて分割します。分割されたデータの塊をRAMに読み込み、そこで利用可能な最速の内部ソートアルゴリズム(例えば、クイックソートやヒープソートなど)を使用して、その塊を完璧に整列させます。この整列された小ブロックのことを「ラン(Run)」と呼びます。
整列が完了したランは、すぐに外部記憶装置に書き出されます。このステップをデータ全体に対して繰り返し実行することで、入力ファイル全体が、多数の整列済みラン(ファイル)として外部記憶装置に格納されることになります。このフェーズで重要なのは、RAMを最大限に活用し、できるだけ長いランを生成することです。長いランであればあるほど、次の併合フェーズでのI/O回数を減らすことができるからです。
2. 併合(マージ)フェーズ
次に、外部記憶装置上に存在する複数のランを、段階的に一つに統合(併合)していきます。このプロセスは、マージソートの中核となる動作です。
通常、外部マージソートでは、I/O効率をさらに高めるために、多方向マージ(K-wayマージ)が採用されます。これは、一度に$K$個のランを同時に読み込み、それぞれのランの先頭要素を比較して、最小の要素(または最大の要素)を結果ファイルに書き出すという操作を繰り返す手法です。この$K$の値は、利用可能な主記憶バッファのサイズによって決定されます。
$K$個のランを併合して、より大きな一つのランを作成し、それを再び外部記憶装置に書き出します。この併合操作を繰り返すことで、ランの総数が減少し、ランのサイズが指数関数的に増大していきます。最終的に、すべてのランが一つに併合されたとき、巨大なデータ全体が完全に整列された状態となります。
アルゴリズムと計算量の観点
外部マージソートは、「アルゴリズムと計算量」の文脈において、比較回数ベースの計算量としては内部ソートのマージソートと同様に$O(N \log N)$を実現します。これは非常に効率的なアルゴリズムであることを示しています。
しかし、外部ソートの真のコストは、計算時間ではなく、I/O時間にあります。I/O回数は、データの読み書きにかかる時間(シーク時間や転送時間)に直結します。多方向マージ($K$-wayマージ)を採用することで、併合フェーズにおけるI/O操作の回数は$\log_K N$に比例して減少します。つまり、同時に併合するランの数($K$)を大きくするほど、ディスクアクセス回数が劇的に減少し、ソートの全体時間が短縮されるというわけです。外部マージソートは、単なる計算量の理論値だけでなく、物理的なハードウェアの特性まで考慮した、実用的なアルゴリズムの勝利と言えるでしょう。
具体例・活用シーン
外部マージソートは、私たちが普段利用している高度