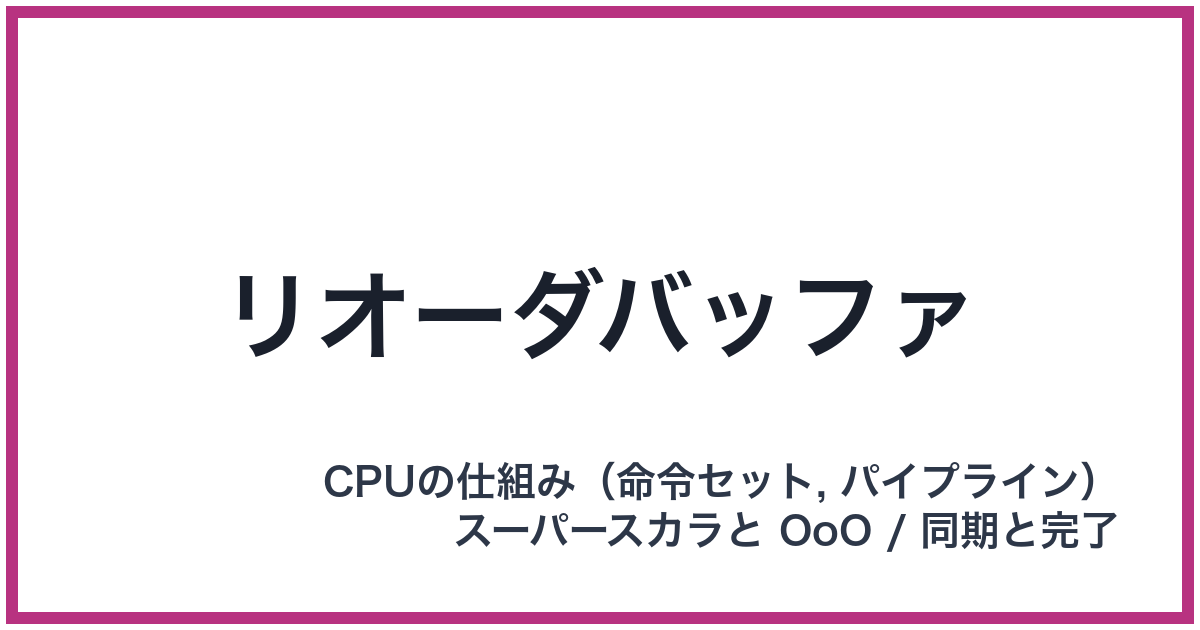リオーダバッファ
英語表記: Re-order Buffer
概要
リオーダバッファ(ROB)は、現代の高性能CPUが採用するアウト・オブ・オーダー実行 (OoO: Out-of-Order Execution) の結果を、元のプログラム順序(イン・オーダー)に同期させ、確定(完了/コミット)させるために不可欠な一時記憶領域です。これは、CPUが命令を効率的にバラバラに処理しても、外部からはあたかも順序通りに実行されたかのように見せるための「最終チェックポイント」の役割を担っています。特に、CPUの仕組み(命令セット, パイプライン)におけるスーパースカラとOoOの文脈では、処理の高速化と、正確な状態維持(同期と完了)を両立させるための心臓部と言えます。
詳細解説
OoO実行とROBの必要性(文脈:スーパースカラと OoO)
リオーダバッファの存在意義を理解するには、まずCPUのスーパースカラとアウト・オブ・オーダー実行(OoO)の仕組みを把握しておく必要があります。スーパースカラとは、複数の命令を同時に実行できる能力を指し、OoOはその能力を最大限に引き出すために、命令間の依存関係がない限り、プログラム上の順番を無視して先に処理を進めてしまう手法です。これは本当に賢い方法で、CPUの処理能力を劇的に向上させました。
しかし、命令をバラバラに実行してしまうと、深刻な問題が発生する可能性があります。例えば、ある命令が途中で例外(エラー)を発生させた場合、その後の命令の結果がすでにレジスタやメモリに書き込まれていたら、プログラムの処理状態が矛盾してしまいます。もし、エラーが発生した命令以降の結果が確定(コミット)されてしまうと、プログラムの正確な再開やデバッグが不可能になってしまいますよね。
ここでROBが登場します。ROBは、パイプラインの途中で実行が完了した命令の結果を、すぐにレジスタやメモリに書き込まず、一時的に保持する「待合室」として機能します。これにより、実行の高速化を享受しつつ、結果の確定は厳密にプログラム順序を守ることができるのです。
動作原理:発行、実行、完了(文脈:同期と完了)
ROBの動作は、パイプラインの最終段階である「同期と完了」フェーズと密接に関わっています。このフェーズこそが、OoO実行の成果を外部に公開する際の秩序を保証する鍵です。
-
発行 (Issue/Dispatch):
命令がデコードされ、実行ユニットへ送られる際、同時にROB内に新しいエントリ(記録枠)が作成されます。このエントリには、その命令が本来プログラム上の何番目の命令であるか(元の順序)が厳密に記録されます。命令がシステムに入った瞬間から、ROBがその命令の「戸籍」を管理し始めるイメージです。 -
実行 (Execution):
実行ユニットが命令を処理します。この処理は、データ依存性さえなければ完全に順不同(OoO)で行われます。結果が出ると、その結果は一時的にROB内の対応するエントリに格納されます。この段階では、結果はまだ「仮」の状態であり、CPUの外部状態(レジスタやメモリ)には一切反映されません。 -
完了/リタイア (Commit/Retire):
ここがROBの最も重要な役割です。ROBは、格納されているエントリを、プログラムの元の順序(イン・オーダー)に従って先頭からチェックします。先頭の命令が「実行完了」しており、かつ「例外なし」であることを確認できた場合、その命令の結果を正式にレジスタファイルやメモリに書き込みます。この最終的な書き込み処理を「コミット」または「リタイア」と呼びます。
この仕組みがあるため、たとえ10番目の命令が1番目の命令より先に実行完了しても、1番目の命令がコミットされるまでは、10番目の命令の結果は確定されません。これにより、例外が発生した場合は、その命令以降のROB内の結果はすべて破棄され、正確な状態への復帰が保証されるのです。これは、高速化と信頼性を両立させる、見事な設計だと思います。
キーコンポーネント
ROBの各エントリは、命令のライフサイクルを追跡するために、非常に重要な情報を保持しています。
- 命令識別子 (Program Counter/Sequence Number): その命令が本来持つべき順序を示す番号です。これが「イン・オーダー」コミットの基準となります。
- ステータス: その命令が現在「実行中」「実行完了