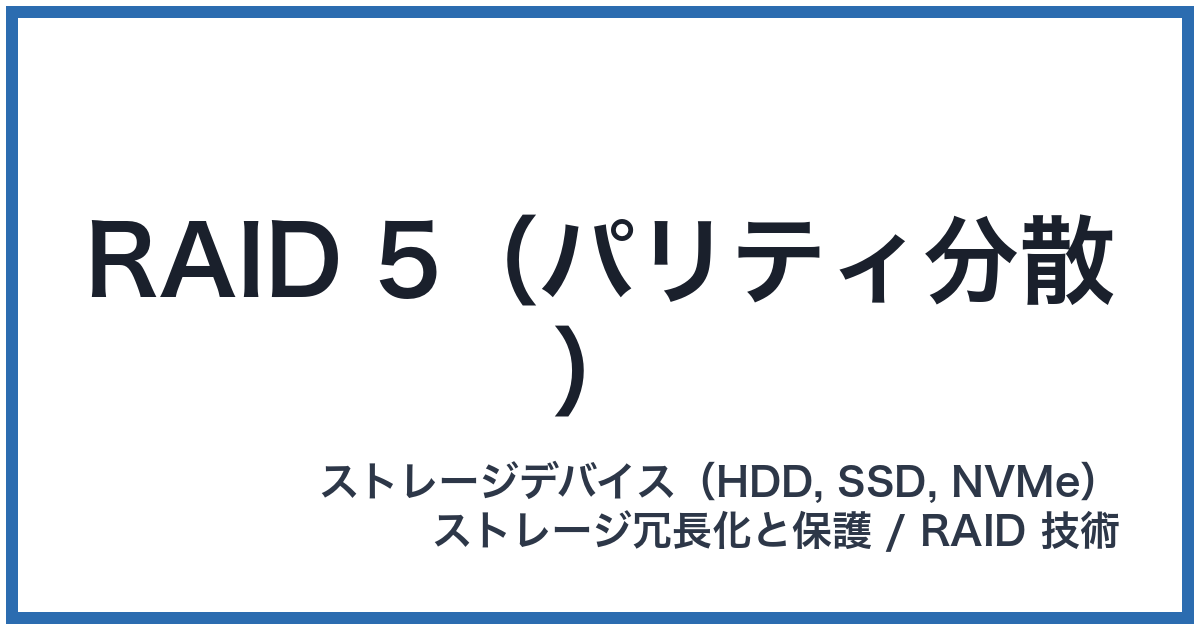RAID 5(パリティ分散)(レイドファイブ)
英語表記: RAID 5 (Distributed Parity)
概要
RAID 5(レイドファイブ)は、複数のストレージデバイス(HDDやSSD)を組み合わせて、データ保護(冗長化)とパフォーマンス向上を両立させる「RAID 技術」の中でも、特に広く普及している構成レベルです。この技術の最大の特徴は、データブロックと同時に生成される誤り訂正情報である「パリティ」を、参加しているすべてのドライブに分散して配置する点にあります。ストレージ冗長化と保護の観点から見ると、RAID 5は、単一のドライブが故障してもシステム全体の稼働を維持できる耐障害性を持ちながら、ディスク容量の利用効率も比較的高い、バランスの取れたソリューションを提供します。
詳細解説
RAID 5は、ストレージデバイス(HDD, SSD, NVMe)の分野において、データの安全性とアクセス速度を両立させるための非常に洗練された技術です。特に、容量効率を犠牲にせずに冗長性を確保するという点で、ストレージ冗長化と保護のカテゴリで重要な位置を占めています。
動作原理:ストライピングとパリティ分散
RAID 5を構成するには、最低でも3台のストレージデバイスが必要です。動作原理は以下の2つの要素に基づいています。
-
データのストライピング(分散配置):
入力されたデータは細かく分割され、複数のディスクに分散して同時に書き込まれます。これはRAID 0と同じ手法であり、並列処理によって読み出し性能を大幅に向上させます。 -
パリティの分散配置:
分割されたデータブロック群から、排他的論理和(XOR演算)を用いてパリティ情報が計算されます。RAID 5では、このパリティ情報を特定のドライブに集めるのではなく、ストライピングされたデータブロック群とは別のドライブに、ローテーションしながら分散して書き込みます。
この「パリティ分散」のおかげで、パリティ情報が特定のボトルネックとなるドライブに集中することがありません。もし1台のディスクが故障した場合、失われたデータブロックは、残りのディスクに残されたデータブロックと、分散配置されていたパリティ情報を使って、瞬時に再計算し復元することが可能です。この復元プロセスを「リビルド(再構築)」と呼びます。
なぜストレージ冗長化に優れているのか
RAID 5がストレージ冗長化と保護の技術として優れているのは、以下のバランスにあります。
- 容量効率の高さ:
RAID 1(ミラーリング)では、冗長化のために総容量の半分を消費しますが、RAID 5ではパリティ領域として消費されるのは全体の容量のうち1台分のみです。例えば、1TBのディスクを4台使った場合、RAID 1では2TBしか使えませんが、RAID 5では3TBを利用できます。容量効率を重視する環境では非常に魅力的です。 - 高速な読み出し性能:
複数のディスクから同時にデータを読み出すため、非常に高速なデータアクセスが可能です。
課題:ライトペナルティとリビルド時間
一方で、RAID 5には書き込み(ライト)処理において少し複雑な手順が必要となり、これが性能上の課題となることがあります。新しいデータを書き込む際、システムは以下の手順を踏む必要があります(RMW: Read-Modify-Write)。
- 既存のデータとパリティを読み出す。
- 新しいデータと既存のデータを使って、新しいパリティを計算する。
- 新しいデータと新しいパリティの両方を書き込む。
この複数の読み書きを伴う処理(ライトペナルティ)のため、書き込み頻度が非常に高い環境では性能が低下しやすいという側面があります。
さらに、現代のストレージデバイス(HDD, SSD, NVMe)が大容量化するにつれて、ディスク故障時のリビルドにかかる時間が非常に長くなっています。リビルド中に別のディスクが故障する可能性(ダブルフォールト)が高まるため、より高い耐障害性を持つRAID 6(2台故障まで許容)へ移行する企業も増えています。しかし、中規模環境やコストを重視する環境においては、RAID 5は依然として現役で活躍している素晴らしい冗長化技術だと言えます。
具体例・活用シーン
RAID 5のパリティ分散の仕組みは、データ保護を必要とする多くのITインフラで活用されています。これは、ストレージデバイスの信頼性を高める上で非常に実用的な選択肢です。
活用シーン
- 中小企業のサーバー環境:
コストを抑えつつ、サーバーのダウンタイムを防ぎたいファイルサーバーやアプリケーションサーバーのストレージとして最適です。容量効率が高いため、導入コストを抑えられます。 - 開発環境やテスト環境:
本番環境ほどの超高速な書き込み性能は求められないが、データが失われると困る開発用データベースなどで利用されます。
初心者向けアナロジー:持ち回りチェック担当制
RAID 5の仕組みを、プロジェクトチームでの「持ち回りチェック担当制」に例えて解説してみましょう。
あなたのチームは4人(ディスクD1, D2, D3, D4)で、お客様向けの重要な資料を作成しています。資料(データ)は4つのパートに分かれており、D1, D2, D3の3人が自分の担当パートを作成します。
**ここでRA