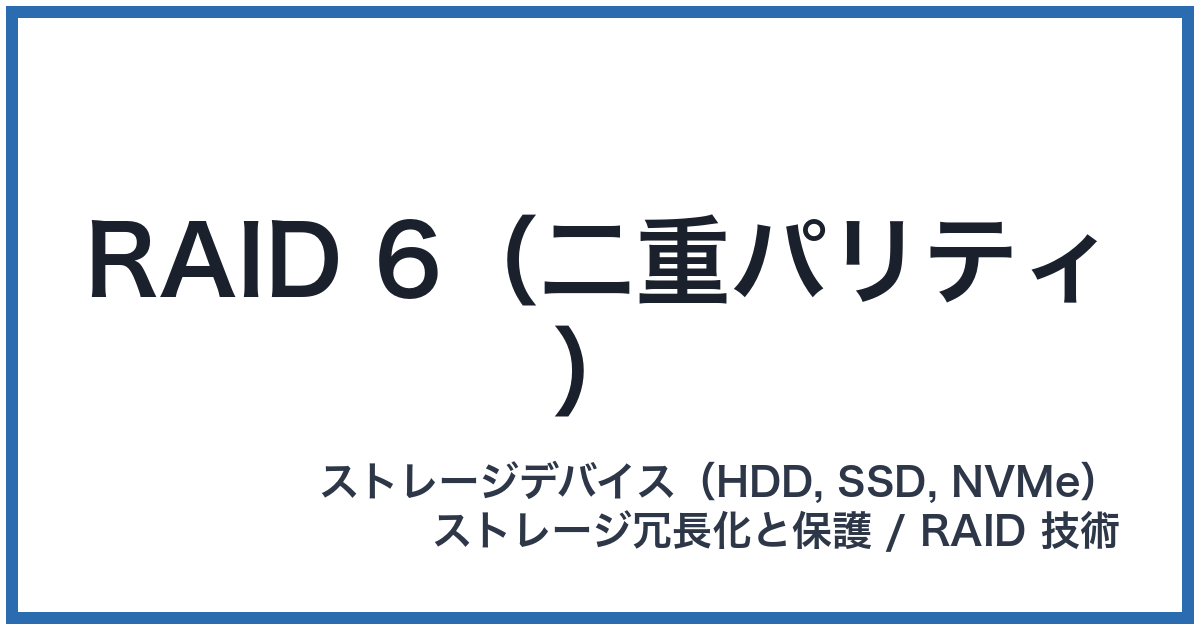RAID 6(二重パリティ)(レイドシックス)
英語表記: RAID 6 (Dual Parity)
概要
RAID 6は、複数の物理ストレージデバイス(HDDやSSD)を組み合わせてデータを保護するRAID技術の一つで、特に高い耐障害性を追求した方式です。これは、私たちが扱うストレージデバイスの信頼性を高めるための「ストレージ冗長化と保護」の重要な柱となっています。最大の特徴は「二重パリティ」を採用している点にあり、これにより同時に2台のディスクが故障してもデータ損失を防ぐことができる、非常に堅牢なシステムを構築できます。
この技術は、物理的な障害からデータを守るための「RAID 技術」の中でも、特にミッションクリティカルな環境や、大容量化に伴い故障リスクが高まるストレージシステムにおいて、標準的な保護策として広く利用されているのです。
詳細解説
目的と位置づけ
RAID 6の主要な目的は、システムのダウンタイムを最小限に抑え、データの可用性を極限まで高めることです。RAID 5(シングルパリティ)は1台のディスク故障までしか許容しませんが、近年のストレージデバイス(特に大容量HDD)は、容量が増えるほどリビルド(データ復旧)にかかる時間が長くなります。リビルド中に別のディスクが故障する「二重故障」のリスクは無視できなくなりつつあります。
RAID 6は、この二重故障のリスクに対応するために開発されました。この技術は、ストレージデバイスの故障という避けられない事態に対し、確実な「ストレージ冗長化と保護」を提供する、非常に頼もしい存在です。
動作原理:二重パリティの仕組み
RAID 6を実現するためには、最低でも4台のディスクが必要です(データディスクN台 + パリティディスク2台)。
RAID 6の核心は、2種類の独立したパリティ情報(PパリティとQパリティ)を生成し、これをデータと共にすべてのディスクに分散して書き込む点にあります。
- Pパリティ(標準パリティ): これは一般的なRAID 5で使われるXOR演算に基づいたパリティです。1台目の故障に対応するための情報となります。
- Qパリティ(追加パリティ): これはPパリティとは異なる、ガロア体演算(Reed-Solomon符号など)を用いた複雑な計算によって生成されるパリティです。このQパリティが、2台目の故障に対応するための復元情報を提供します。
データが書き込まれる際、システムはデータブロックに対してPとQという二つの異なる計算を行い、その結果を異なるディスクに書き込みます。もし1台のディスクが故障した場合、残りのディスクとパリティ情報(PまたはQのいずれか)を使ってデータを復元できます。さらに2台目のディスクが故障しても、残されたデータと二つのパリティ情報(PとQ)を用いて、失われた2つのデータブロックを数学的に完全に復元することが可能になるのです。
性能特性
RAID 6は非常に安全性が高い反面、性能、特に書き込み性能においてはトレードオフがあります。
- 書き込み処理: データを書き込むたびに、PパリティとQパリティという2種類のパリティを計算し、合計で2つのパリティブロックを書き込む必要があるため、RAID 5やRAID 10と比較してCPU負荷が高くなり、書き込み速度が低下する傾向があります。
- 読み取り処理: 読み取りに関しては、パリティ計算が不要なため、RAID 5と同等か、ディスク台数に応じた高速なアクセスが期待できます。
しかし、現代の高性能なストレージコントローラやSSD(NVMeを含む)の利用により、この書き込みペナルティは実用上、あまり問題にならないケースが増えてきています。重要なのは、多少の性能低下を受け入れても、極めて高い「ストレージ冗長化と保護」のレベルを確保すること、という判断がRAイド6を選択する理由となるのです。
具体例・活用シーン
RAID 6は、信頼性が最優先される環境で真価を発揮します。
- 大規模ストレージシステム(SAN/NAS): 企業の大容量ファイルサーバーや、数十テラバイトを超えるデータレイクなど、多くのディスクを搭載するシステムでは、ディスク故障の確率が統計的に高くなります。RAID 6を採用することで、リビルド中に安心して運用を継続できます。
- 仮想化基盤(VMware, Hyper-V): 多数の仮想マシンが稼働するストレージ基盤において、もしストレージ障害が発生すれば、業務全体が停止する恐れがあります。RAID 6は、基盤全体の安定性を担保するための必須の選択肢となります。
- アーカイブ/バックアップターゲット: 長期間データを保存する用途では、ディスクの老朽化による故障リスクも高まります。RAID 6は、バックアップデータそのものの保護にも適しています。
アナロジー:二重の監視員によるデータ保護
RAID 6の二重パリティの仕組みは、重要なデータが詰まった金庫室(ストレージアレイ)を、二人の独立した監視員が守っている状況に例えることができます。
RAID 5(一重パリティ)の場合: 監視員Aが、金庫室内のすべての貴重品(データ)の目録(パリティ)を作成し、それを保管しています。もし貴重品が一つ盗まれても、監視員Aの目録から何が失われたかを特定し、復元することができます。しかし、もし貴重品が盗まれたと同時に、監視員Aが病欠して目録が失われた場合、もう何が失われたかを知る術はありません。これが二重故障時のデータ損失です。
RAID 6(二重パリティ)の場合: 監視員A(Pパリティ)に加えて、まったく異なる計算方法で目録を作成する監視員B(Qパリティ)が存在します。彼らは独立して働いていますが、協力して金庫室を守っています。
もし貴重品が2つ同時に盗まれたとしても、監視員Aと監視員Bがそれぞれ持っている目録情報を突き合わせることで、「貴重品1と貴重品2が失われた」という事実だけでなく、「貴重品1は〇〇で、貴重品2は△△である」という中身そのものを正確に再構成できるのです。
このように、RAID 6は二重の保護層を持つことで、ストレージデバイスの故障が発生しても、業務の継続性を確保する「ストレージ冗長化と保護」の究極的な形を提供していると言えるでしょう。
資格試験向けチェックポイント
ITパスポート試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験において、RAID 6は「ストレージ冗長化と保護」の具体的な技術として頻出します。特に、RAID 5との違いを明確に理解しておくことが重要です。
- 必須ディスク台数: RAID 6の最小構成は4台以上である、という数字は必ず覚えておきましょう。これは、データディスク2台とパリティ専用ディスク2台(Pパリティ用とQパリティ用)が必要なためです。
- 耐障害性(許容故障数): 許容できる同時故障ディスク数は2台です。これは、RAID 5の1台、RAID 1の1台(または2台)、RAID 10の構造的な許容数と比較して問われることが多いポイントです。
- キーワード:二重パリティ: RAID 6を指す別名として「二重パリティ」が使われます。この用語は、なぜ2台故障しても大丈夫なのかを理解するための鍵となります。
- リビルド中の安全性: 大容量ディスク環境におけるリビルド時間延長と、それに伴う二重故障リスクの増大に対する解決策としてRAID 6が位置づけられます。応用情報技術者試験などでは、このリスクと対策の関係を問う問題が出題されやすいです。
- 性能のトレードオフ: 高い安全性(冗長性)と引き換えに、書き込み速度に一定のペナルティが発生すること(パリティ計算が二重になるため)を理解しておきましょう。
関連用語
- 情報不足(ただし、学習を進める上で「RAID 5(シングルパリティ)」「パリティ」「ホットスペア」「リビルド」などの用語を合わせて確認することで、RAID 6がなぜ重要なのか、その文脈を深く理解することができます。)