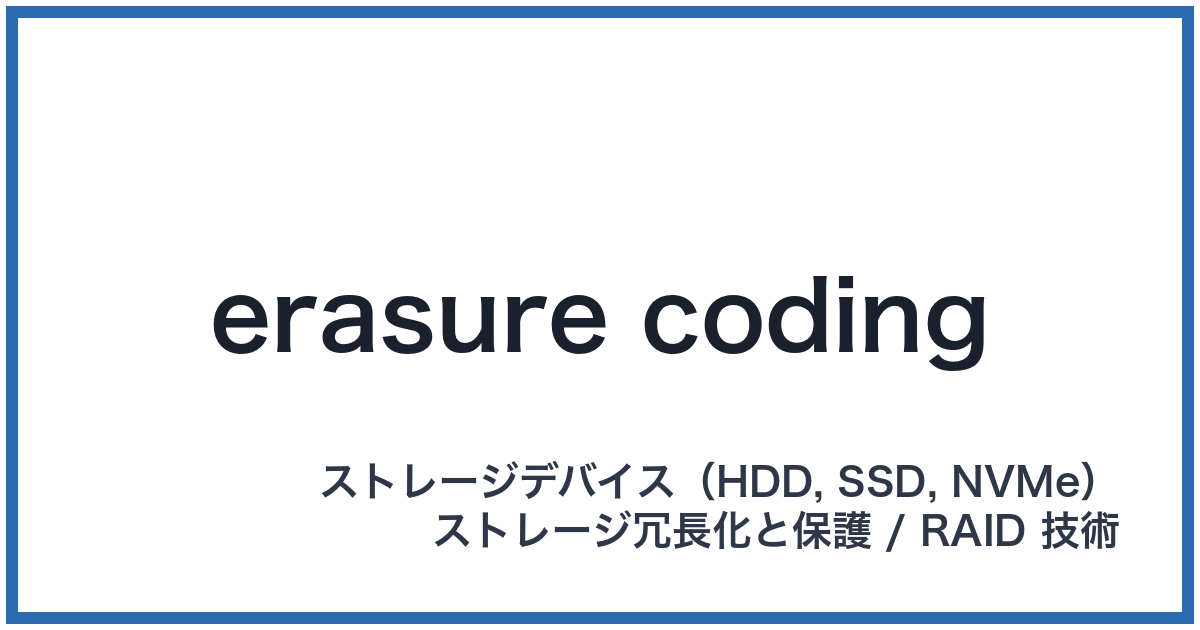erasure coding(イレイジャーコーディング)
英語表記: Erasure Coding
概要
イレイジャーコーディングは、ストレージ冗長化と保護を実現するための高度なデータ保護技術であり、従来のRAID技術(RAID 5やRAID 6)の課題を克服するために開発されました。これは、オリジナルのデータを複数の断片に分割し、さらに冗長性を持たせるためのパリティ情報を付加することで、データの一部が消失しても完全に復元できるようにする仕組みです。特に、ペタバイト級のデータを扱う大規模な分散ストレージシステムやオブジェクトストレージにおいて、高い冗長性と効率的なディスク利用率を両立させるために不可欠な技術となっています。
詳細解説
目的と背景:RAID技術の進化系として
この技術がなぜストレージデバイスの保護(ストレージ冗長化と保護)の文脈で重要なのかというと、従来のRAID技術が抱える限界を解決するためだからです。RAID 6は2台までのドライブ故障に耐えられますが、数十テラバイト、ペタバイト規模の環境では、ドライブの台数が非常に多くなり、さらに大容量化によって故障したドライブのデータ再構築(リビルド)に膨大な時間がかかってしまいます。このリビルド中に別のドライブが故障する「二重障害の窓」が広がり、データ消失のリスクが高まるのが大きな問題でした。
イレイジャーコーディングは、この問題を解決し、より柔軟で強固な冗長性を提供します。これは、従来のRAIDが「固定された構成(例:RAID 6は常に2重パリティ)」であるのに対し、ECは必要な冗長度を自由に設定できる点が優れているのです。
動作原理:K+M符号化の仕組み
イレイジャーコーディングの核となる動作原理は、「K+M符号化」と呼ばれる手法です。
- データ分割(K): まず、オリジナルのデータをK個のデータ断片(チャンク)に分割します。Kは任意の数で設定されます。
- パリティ生成(M): 次に、このK個のデータ断片から、複雑な数学的アルゴリズム(多くの場合、リード・ソロモン符号など)を用いてM個のパリティ断片を生成します。Mもまた任意の数で設定されます。
- 分散配置: 合計K+M個の断片(データK+パリティM)を、異なるストレージデバイスやノードに分散して保存します。
このシステムでは、合計K+M個の断片のうち、任意のM個までの断片が失われても、残りの断片から完全なデータを復元することが可能です。例えば、K=10、M=4と設定した場合、データは10個に分割され、4個のパリティが生成されます。合計14個の断片が分散されますが、このうち最大4個の断片(データ断片でもパリティ断片でも可)が失われても、残りの10個の断片があればデータを復元できるわけです。
効率性と柔軟性
この「KとMの比率」を調整できることが、ECの最大のメリットです。
- ディスク効率の向上: 冗長化のために必要なオーバーヘッド(パリティの容量)を、従来のRAIDよりも細かく調整できるため、ストレージの利用効率を大幅に高めることができます。例えば、RAID 6は常に約50%のオーバーヘッド(最低4台構成で2台がパリティ)が必要ですが、ECでK=10, M=2と設定すれば、オーバーヘッドはわずか2/12(約16.7%)に抑えられます。
- 大規模環境への適合: 大量のノードにデータを分散させることで、特定のノードに負荷が集中するのを防ぎます。また、故障が発生した際も、再構築の処理を多数のノードで分担できるため、リビルド時間を短縮し、データ保護の堅牢性を高めることができます。
イレイジャーコーディングは、まさにRAID技術が大規模化の波に対応するために編み出した、賢い解決策だと言えるでしょう。
具体例・活用シーン
イレイジャーコーディングは、私たちが普段利用しているクラウドサービスや大規模なデータセンターの裏側で、重要な役割を果たしています。
1. オブジェクトストレージでの利用
Amazon S3やAzure Blob Storageといった、クラウドのオブジェクトストレージサービスでは、データ保護の標準技術としてイレイジャーコーディングが採用されています。これらのサービスは数千台、数万台のストレージデバイスで構成されており、従来のRAIDでは管理も効率も成り立ちません。ECを使うことで、数十台のサーバーが故障してもデータが保護されるような、極めて高い堅牢性を実現しているのです。
2. データ復元の「魔法のレシピ」
イレイジャーコーディングの仕組みを理解するための良いアナロジーとして、「魔法のレシピ」の話をしましょう。
あなたは非常に重要な「秘密のレシピ(データ)」を持っています。このレシピはあまりに重要なので、絶対に失いたくありません。
- レシピの分割(K): まず、このレシピを10個の小さなステップ(K=10)に分割し、それぞれを異なる10人の友人(ノード)に預けます。
- 復元用コードの作成(M): さらに、この10個のステップを組み合わせることで、レシピ全体を復元できる「魔法の復元コード(パリティ情報)」を4つ(M=4)作成します。この4つのコードも、別の4人の友人(ノード)に預けます。
これで、合計14人の友人にレシピの断片と復元コードが分散されました。
もし、レシピの一部を持っていた友人や、復元コードを持っていた友人を含めて、最大4人(M=4)が急にいなくなってしまったとしても、残りの10人の持っている断片とコードを組み合わせれば、レシピ全体を完璧に復元できます。
従来のRAID 6は、この話で言えば「レシピを10人に預け、復元コードは常に2つだけ作る」という固定ルールです。しかし、ECを使えば、「レシピの重要度に応じて、復元コードを4つにするか、6つにするか、柔軟に決められる」というわけです。これにより、効率よく、かつ強固にデータを守れるのです。
資格試験向けチェックポイント
イレイジャーコーディングは、特に応用情報技術者試験や高度なネットワーク・ストレージの知識を問う試験で出題される可能性が高まっています。ストレージ冗長化と保護の最新技術として、従来のRAIDとの違いを明確に理解しておくことが重要です。
- RAID技術の延長線上にあることの理解: ECは、RAID 5/6のパリティ分散の概念を、分散システム向けに一般化・高度化した技術であると認識しておきましょう。
- 主要な適用分野: オブジェクトストレージ、大規模分散ファイルシステム(Hadoop HDFSなど)といった、ペタバイト級のデータを取り扱う環境で利用される点が頻出ポイントです。
- K+M符号化の概念: 「K個のデータ断片とM個のパリティ断片から構成され、M個までの障害に耐えられる」という仕組みを問う問題が出やすいです。特に、障害耐性(M)とストレージ効率(K/(K+M))がトレードオフの関係にあることを理解しておきましょう。
- メリット: 従来のRAIDと比較して、「ディスク利用効率が高い」「障害耐性の柔軟性が高い」「リビルド時間が短縮できる(分散処理のため)」といった点が、選択肢として問われます。
- リード・ソロモン符号: ECの実現に用いられる代表的な符号化方式として、リード・ソロモン符号(Reed-Solomon Codes)の名前が知識問題として出題されることがあります。
関連用語
イレイジャーコーディングを理解する上で、以下の用語も重要となりますが、本記事の執筆時点では詳細な情報が不足しています。
- 情報不足: RAID 6(RAID技術の比較対象として)、オブジェクトストレージ(主要な適用先として)、リード・ソロモン符号(ECを実現する主要なアルゴリズムとして)、分散ファイルシステム(大規模環境における文脈として)などの詳細な情報が不足しています。これらの用語の定義や関連性について、追加の情報提供が必要です。