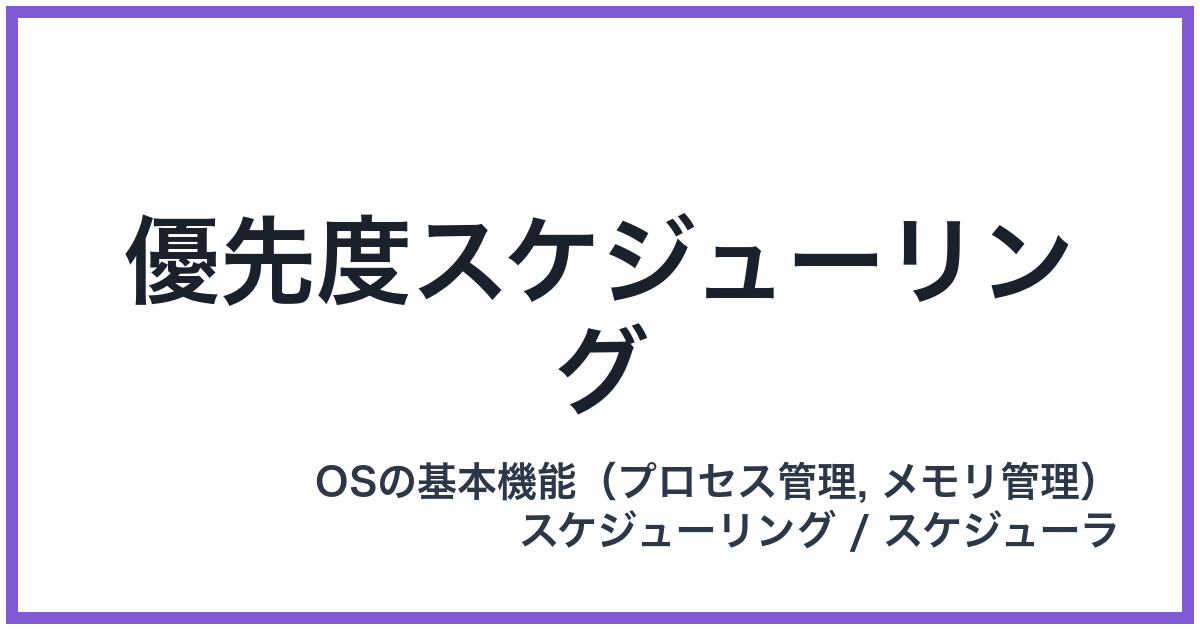優先度スケジューリング
英語表記: Priority Scheduling
概要
優先度スケジューリングとは、OSの基本機能であるプロセス管理において、CPUリソースをどのプロセスに割り当てるかを決定するスケジューリングアルゴリズムの一つです。実行待ち状態にある複数のプロセスに対し、あらかじめ設定された「優先度」に基づき、最も優先度の高いプロセスから順にCPUの利用権を付与する方式を採用しています。このアルゴリズムは、OSのスケジューラが採用する最も重要な決定ロジックであり、システムの応答性や公平性を左右する鍵となります。
詳細解説
目的と位置づけ
この概念は、「OSの基本機能(プロセス管理, メモリ管理)→ スケジューリング → スケジューラ」という階層構造の中で、特に「スケジューリング」の核となる部分です。スケジューリングの目的は、限られたCPU時間を、実行を要求している多数のプロセス間でいかに効率的かつ公平に分配するか、という点にあります。
優先度スケジューリングの最大の目的は、システムの要件に応じて重要なタスクを優先的に処理することです。例えば、ユーザーが入力したキーボード操作やマウス操作に対応するプロセス(応答性が重視される)は、バックグラウンドで動いている大規模な計算プロセス(スループットが重視される)よりも高い優先度を持つべきです。
動作原理とコンポーネント
優先度スケジューリングが機能するためには、各プロセスが「優先度」という数値情報を持つ必要があります。これは通常、プロセス制御ブロック(PCB)内に格納されています。
スケジューラ(ディスパッチャの前段階で動作する選択機構)は、実行待ちキューの中から、この優先度フィールドをチェックし、最も高い優先度を持つプロセスを選択します。
優先度の設定方法には、大きく分けて二つの種類があります。
1. 静的優先度 (Static Priority)
プロセスが生成された時点で優先度が固定され、実行中に変化しません。設定がシンプルである反面、システムの状況変化に対応できないという欠点があります。例えば、非常に重要なプロセスを静的に高優先度に設定した場合、そのプロセスがCPUを占有し続ける可能性があります。
2. 動的優先度 (Dynamic Priority)
プロセスの実行状況や待機時間に応じて、優先度が変動します。OSは、プロセスが長期間待機していると優先度を上げたり、CPUを使いすぎていると優先度を下げたりといった調整を動的に行います。
動的優先度が非常に重要になる背景には、「飢餓(Starvation)」の問題があります。飢餓とは、低優先度のプロセスがいつまでもCPUを割り当てられず、永久に実行されない状態を指します。
この飢餓を防ぐために導入されるのがエージング(Aging)という仕組みです。エージングとは、待機時間が長くなるにつれて、プロセスの優先度を徐々に引き上げていく手法です。これにより、どんなに優先度の低いプロセスであっても、いずれは実行される機会を得ることが保証されます。これは、スケジューラがプロセス管理の公平性を担保するために欠かせないメカニズムだと私は感じています。
プリエンプティブと非プリエンプティブ
優先度スケジューリングには、さらに「プリエンプティブ(Preemptive)」と「非プリエンプティブ(Non-preemptive)」の区別があります。
- 非プリエンプティブ: 高優先度のプロセスが到着しても、現在実行中のプロセスが自発的にCPUを開放するまで待機します。
- プリエンプティブ: 高優先度のプロセスが到着した場合、現在実行中のプロセスを即座に中断(プリエンプト)させ、新しい高優先度プロセスにCPUを割り当てます。現代のOSの多くは、応答性を高めるためにこのプリエンプティブ方式を採用しています。
この優先度スケジューリングの採用によって、OSは単にタスクを処理するだけでなく、「どのタスクがより重要か」という判断をシステムレベルで行うことができるようになっているのです。
具体例・活用シーン
優先度スケジューリングは、私たちが日常的に使用するほとんどのマルチタスクOS(Windows, macOS, Linuxなど)の中核をなす機能です。
リアルタイムOSでの利用
例えば、工場で使われる制御システムや医療機器など、応答時間が厳密に決められている「リアルタイムOS (RTOS)」では、優先度スケジューリングが不可欠です。センサーからのデータ処理や緊急停止信号の処理は、他のプロセスよりも極めて高い優先度を与えられ、瞬時に実行されるように設計されています。これは、OSがプロセス管理を通じて、物理的な安全性を担保している例と言えるでしょう。
具体的なアナロジー:病院のトリアージ
優先度スケジューリングの概念を理解するための最も分かりやすい比喩は、病院の救急外来におけるトリアージ(Triage)です。
病院の救急外来には、風邪をひいた軽症の患者から、命に関わる重篤な怪我を負った患者まで、様々な人が同時に到着します。もし先着順(FCFS: First Come, First Served)で診察を始めたら、軽症の患者が先に診察を受けている間に、重篤な患者の命が危険にさらされてしまうかもしれません。
ここで登場するのが、トリアージナース(OSのスケジューラ)です。
- 優先度の決定: ナースは到着した患者(プロセス)一人ひとりの状態を確認し、「今すぐ処置が必要(高優先度)」「待機可能(低優先度)」といったレベル(優先度)を割り当てます。
- 実行の選択: 診察室(CPU)が空くと、ナースは最も優先度の高いラベルが貼られた患者を迷わず選びます。
- 飢餓対策(エージング): もし、中程度の怪我の患者が、高優先度の患者が次々と運ばれてくるせいで何時間も待たされている場合、ナースは定期的にその患者の状態を再評価し、「このままでは危険だ」と判断したら、優先度を少し引き上げて(エージング)、診察を受けられるようにします。
このように、優先度スケジューリングは、限られたリソース(診察室=CPU)を最大限に活かし、最も重要なタスク(命に関わる処置)を最優先で実行するために、OSのプロセス管理機能が備えている非常に合理的な判断システムなのです。
資格試験向けチェックポイント
優先度スケジューリングは、ITパスポートから応用情報技術者試験まで、OSのプロセス管理分野で頻出するテーマです。特に、他のスケジューリングアルゴリズムとの比較や、公平性に関する概念が問われやすいです。
| 資格レベル | 出題傾向と対策のポイント |
| :— | :— |
| ITパスポート | 定義と目的の理解が中心です。「優先度の高いプロセスから実行する」という基本的な仕組みを、FCFS(先着順)やラウンドロビン(時間割当)と比較して理解しましょう。スケジューラがOSのどの部分で機能しているか(プロセス管理内)を把握することが重要です。 |
| 基本情報技術者 | 動作原理と問題点に関する知識が問われます。特に、飢餓(Starvation)が発生するメカニズムとその対策であるエージング(Aging)は頻出です。また、静的優先度と動的優先度の違いを明確に説明できるよう準備してください。プリエンプティブ方式が応答性に優れる点も重要です。 |
| 応用情報技術者 | より高度なOS設計の観点から問われます。リアルタイムOSにおける優先度スケジューリングの役割や、優先度逆転(Priority Inversion)問題など、より専門的な課題解決策が問われることがあります。スケジューリングアルゴリズムの選択が、システムの性能指標(応答時間、スループット、ターンアラウンドタイム)にどう影響するかを定量的に理解する必要があります。|
試験対策のヒント:
「OSの基本機能(プロセス管理, メモリ管理)→ スケジューリング → スケジューラ」という流れの中で、優先度スケジューリングは、単に実行順を決めるだけでなく、OSがシステムリソースの「重要度」を判断する役割を担っていると捉えると理解が深まります。
関連用語
- 情報不足
(注記:関連用語として、FCFS、ラウンドロビン、エージング、飢餓、ディスパッチャ、プロセス制御ブロック(PCB)などが挙げられますが、本インプット材料には具体的な情報が提供されていないため、関連用語の情報は不足しています。これらの用語は、優先度スケジューリングを深く理解する上で非常に重要です。)