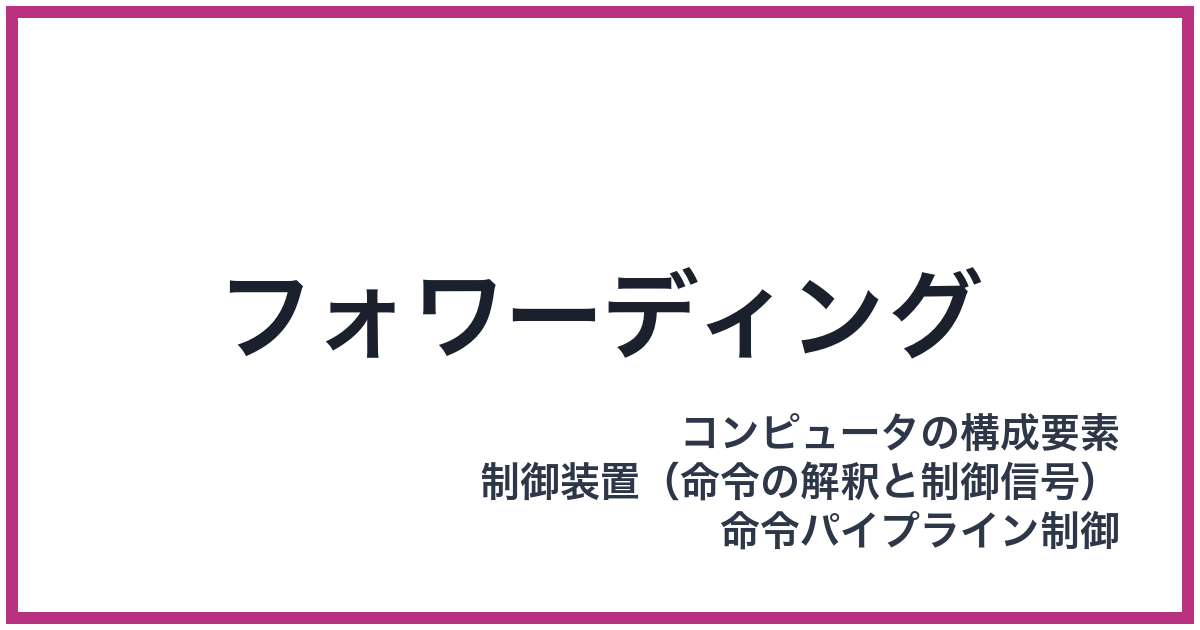フォワーディング
英語表記: Forwarding
概要
フォワーディングとは、高性能なプロセッサの動作を支える「命令パイプライン制御」において、処理の効率を低下させる「データハザード」を解決するための非常に重要な技術です。具体的には、先行する命令が演算結果をレジスタに書き込むのを待たずに、その演算途中の結果を直接、後続の命令の入力として「転送(フォワード)」する仕組みを指します。これにより、命令の実行に必要なデータがすぐに利用可能となり、パイプライン処理が滞る「ストール(失速)」を防ぎ、CPUの処理能力を最大限に引き出すことができるのです。この技術は、制御装置が命令の依存関係を解釈し、適切なタイミングでデータを転送する精密な制御を担っています。
詳細解説
このフォワーディングという概念は、「コンピュータの構成要素」の中でも、特にプロセッサの中核をなす「制御装置」が担当する「命令パイプライン制御」の文脈で理解することが不可欠です。フォワーディングは、パイプライン処理の理想的な効率(毎クロックサイクルで命令を完了すること)を現実のものとするための、制御装置による高度な工夫と言えます。
パイプライン処理とハザードの発生
現代のCPUは、命令処理を複数の段階(フェッチ、デコード、実行、メモリアクセス、ライトバックなど)に分割し、複数の命令を同時に並行して処理する「命令パイプライン」を採用しています。これにより、処理速度が大幅に向上しますが、命令間でデータの依存関係がある場合、問題が発生します。
フォワーディングが対策するのは主に「データハザード」のうち、「Read After Write (RAW) ハザード」と呼ばれるものです。これは、ある命令(A)がレジスタに書き込む結果を、直後の命令(B)が読み込もうとする際に起こります。命令Aがまだ結果を確定させていないにもかかわらず、命令Bが先にデータを要求してしまうと、命令Bは誤った(古い)データを使って処理を進めてしまい、結果が不正になってしまいます。
フォワーディングの目的と動作原理
データハザードが発生した場合、最も単純な対策は、命令Bが命令Aの結果を待つ間、パイプラインを一時停止させる「ストール」です。しかし、ストールが発生すると、せっかく並行処理している命令の流れが途切れてしまい、CPUの性能が大きく低下してしまいます。
フォワーディングの究極の目的は、このストールを回避し、パイプラインの連続性を維持することにあります。
フォワーディングの動作原理は、結果がレジスタファイルに書き込まれるのを待たない点にあります。命令Aが「実行(Execute)」ステージや「メモリアクセス(Memory)」ステージで結果を生成した直後、その結果はまだ最終的な記憶領域(レジスタファイル)には到達していません。フォワーディング機構は、この途中の計算結果を捕捉し、特別な「バイパスパス」を通して、結果を必要としている後続の命令Bの「実行」ステージの入力に直接転送します。
例えば、命令Aが実行ステージで加算を終えた場合、その加算結果はすぐに後続の命令Bに渡されます。これにより、命令Bは、命令Aがパイプラインの最終ステージ(ライトバック)に到達するまで待つ必要がなくなり、命令間の依存関係による遅延が解消されるのです。この迅速なデータの転送経路の確保と制御は、全て「制御装置」の複雑なロジックによって実現されています。
主要コンポーネント
フォワーディングを実現するためには、制御装置内部に以下の重要なコンポーネントが組み込まれています。
- ハザード検出ユニット: 命令間の依存関係を常に監視し、データハザードが発生する正確なタイミングを特定します。どの命令がどのレジスタの値を必要とし、それがどの先行命令によって生成されるかを分析します。
- バイパスパス(転送経路): 演算結果が生成されるステージ(実行ステージやメモリステージの出力)から、後続命令の入力ステージ(実行ステージの入力)へとデータを迂回させるための専用の高速なデータ経路です。
- マルチプレクサ(セレクタ): 後続命令が実行ステージ