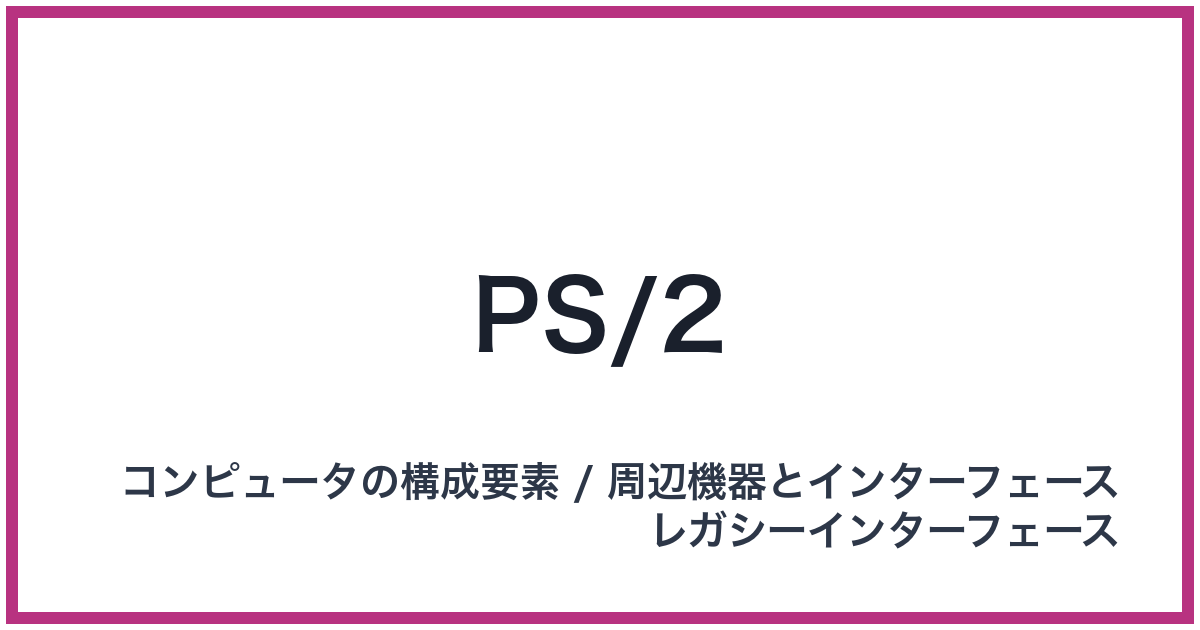PS/2
英語表記: PS/2
概要
PS/2は、主にキーボードとマウスといった入力装置をコンピュータ本体に接続するために使用されていた、丸型の6ピンコネクタを持つシリアルインターフェースです。これは、かつてコンピュータの構成要素として不可欠だった周辺機器とインターフェースの接続方法の一つであり、IBMが1987年に発表した「Personal System/2」シリーズで採用されたことからこの名が付きました。現在では、より汎用性の高いUSBインターフェースにその役割を譲り、この分類における「レガシーインターフェース」として歴史的な位置づけとなっています。
詳細解説
PS/2インターフェースは、コンピュータの構成要素の中でも、ユーザーの操作を司る重要な周辺機器(キーボード、マウス)のために設計されました。このインターフェースの登場以前は、キーボードは大型のATコネクタ(DINコネクタ)を、マウスはシリアルポート(RS-232C)を使用することが一般的でしたが、PS/2はこれらを統合し、専用の小型ポートを提供することでPCの設計をシンプルにしました。
動作原理と特徴
PS/2はシリアル通信方式を採用しており、信号線とクロック線を用いてデータを送受信します。最大の特徴は、キーボードとマウスがそれぞれ専用のハードウェア割り込み(IRQ)を使用するように設計されていた点です。これにより、OSが起動する前のBIOSレベルから確実に入力操作を処理できるという信頼性があり、特に初期のPC環境においては非常に重要視されていました。
しかし、レガシーインターフェースとなった最大の理由が、その設計上の制約にあります。
- 専用ポートの必要性: PS/2は、キーボード用とマウス用で異なるポート(通常、キーボードが紫、マウスが緑に色分けされていました)を必要としました。これは、周辺機器とインターフェースの接続において、ポートの汎用性が低いことを意味します。
- ホットプラグの非対応: 現代のUSBのように、コンピュータの電源が入ったままケーブルを抜き差しする「ホットプラグ」に原則として対応していません。もし電源が入っている状態でPS/2デバイスを抜き差しすると、システムがフリーズしたり、最悪の場合、マザーボード側のPS/2コントローラーが損傷するリスクさえありました。これは利用者にとって非常に不便な点でしたね。
- 拡張性の限界: 基本的にキーボードとマウスの接続に特化しており、他の多様な周辺機器(プリンタ、ストレージなど)を接続する能力はありませんでした。
レガシー化への道
周辺機器とインターフェースの進化は目覚ましく、USB(Universal Serial Bus)の登場により、PS/2はその座を譲りました。USBはホットプラグに対応し、一つのポートで様々な機器を接続でき、さらに電源供給能力も高いという圧倒的な利便性を提供しました。現在、マザーボードからPS/2ポートはほぼ姿を消し、あっても主に互換性の維持や、BIOS設定時などUSBが動作しない環境での入力確保といった、限定的な用途で残るのみとなっています。この歴史的な変遷こそが、PS/2が「レガシーインターフェース」のカテゴリーに分類される所以です。
具体例・活用シーン
PS/2インターフェースは、かつてのPC環境を象徴する存在であり、その使用シーンを振り返ると、レガシー技術ならではの面白さが見えてきます。
-
色分けの記憶:
多くのユーザーにとって、PS/2ポートといえば、マザーボードの背面に並ぶ「紫と緑」の丸い穴のペアを思い出すでしょう。キーボードを紫、マウスを緑に挿すというルールは、当時のPC組み立てや設定の基本中の基本でした。もし逆にしてしまうと、デバイスが認識されず、「あれ?キーボードが動かない!」と慌てた経験を持つ方も多いのではないでしょうか。この色分け自体が、PS/2がキーボードとマウスという特定の周辺機器専用のインターフェースだったことを物語っています。 -
ホットプラグ禁止の儀式:
PS/2時代のPCユーザーは、キーボードやマウスを交換する際、必ずPCの電源を完全に落とすという「儀式」を行う必要がありました。この操作は、現代のUSB接続に慣れた方には信じられないかもしれませんが、当時は機器を安全に扱うための常識だったのです。もし間違って電源オンのまま抜くと、システムが不安定になるというスリルがありました。 -
【比喩】VIPのための専用駐車場
PS/2インターフェースを理解するための良い比喩は、「VIPのための専用駐車場」です。
USBが「誰でも使える大規模な立体駐車場(多くの周辺機器が自由に出入りできる)」だとすれば、PS/2は「キーボードとマウスという二人のVIP専用に、建物の入り口の最も良い場所に確保された、二台分の特別な平面駐車場」のようなものです。
この専用駐車場(PS/2ポート)は、他の車(他の周辺機器)は決して使えません。しかし、キーボードとマウスは、この専用の場所があるおかげで、建物がオープンする前(OS起動前)から、最優先でアクセス(BIOSからの入力)を確保できるという特権を持っていました。
ただし、この駐車場は非常に厳格で、一度駐車したら、建物の警備システム(PCの電源)が完全に停止するまで、絶対に動かしたり、別の車と交換したりしてはいけません(ホットプラグ禁止)。この厳格さと引き換えに、確実な入力保証を得ていたのがPS/2の姿です。
資格試験向けチェックポイント
PS/2はレガシーインターフェースとして扱われますが、基本情報技術者試験や応用情報技術者試験では、インターフェース技術の歴史的変遷や、現行規格(USB)との比較を通じて出題されることがあります。
-
USBとの対比の理解:
PS/2に関する問題は、ほとんどの場合、現代の主流であるUSBとの違いを問う形で出題されます。- 問われるポイント: ホットプラグ対応の有無(PS/2は非対応)、汎用性の違い(PS/2はキーボード・マウス専用)、通信方式(シリアル通信)、レガシー技術としての位置づけ。
- 対策のヒント: 「PS/2は専用性・確実性が高いが、利便性・拡張性に劣る」という構造を覚えておきましょう。
-
レガシーインターフェースの認識:
コンピュータの構成要素を学ぶ上で、周辺機器とインターフェースの進化の過程は重要です。RS-232C(シリアル)、パラレルポート、PS/2、そしてUSBという流れを把握し、PS/2がどの時代の技術であったかを理解しておくことが求められます。 -
色分けと機能の結びつけ:
資格試験では、PS/2ポートの「紫(キーボード)と緑(マウス)」の色分け知識が、基礎的なIT知識として問われることがあります。単純な知識ですが、現代ではなかなか見かけないため、忘れずにチェックしておきたいポイントです。 -
割り込み(IRQ)に関する知識:
PS/2が専用のハードウェア割り込みを使用していた点(割り込みを占有する)は、USBのようにデバイスが動的に割り当てられる方式との違いとして、特に基本情報技術者試験で問われる可能性があります。
関連用語
- 情報不足
- (補足情報: PS/2は、RS-232Cやパラレルポートといった同時期のレガシーインターフェースと対比されることが多いです。また、後継規格であるUSBは、この技術の限界を克服した代表例として関連性が非常に高いです。これらの用語を比較対象として追加検討する必要があります。)