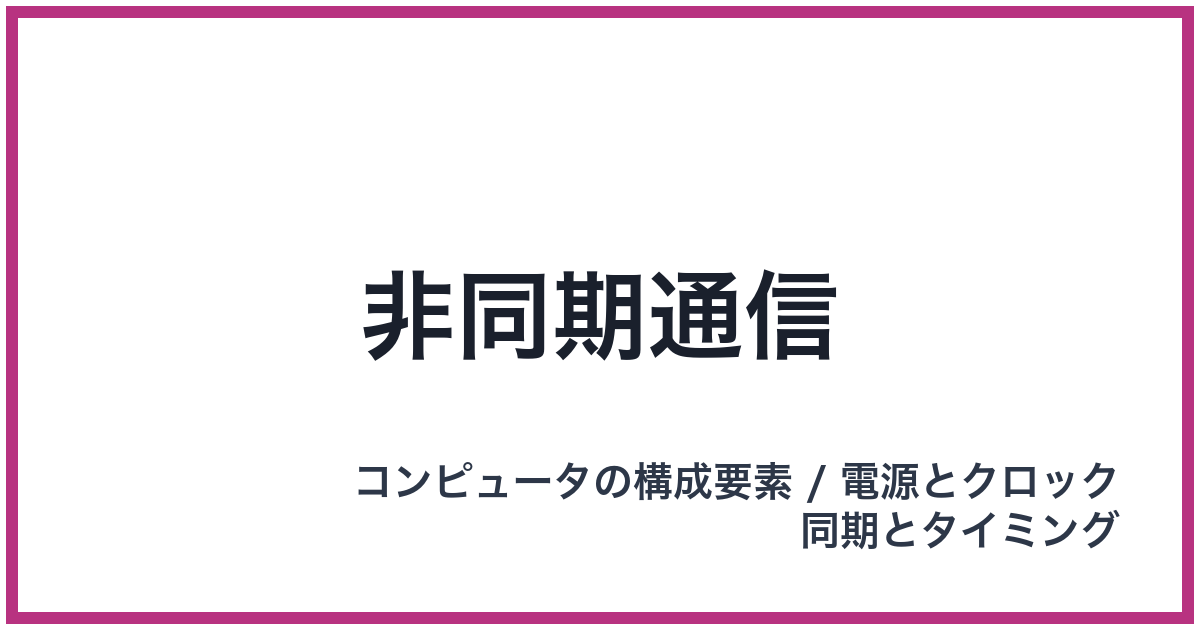非同期通信
英語表記: Asynchronous Communication
概要
非同期通信(Asynchronous Communication)は、「コンピュータの構成要素」がデータをやり取りする際、送信側と受信側が共通のクロック信号(タイミング)に厳密に同期せずに行う通信方式のことを指します。これは、特に速度や動作タイミングが異なる複数の構成要素(例えば、低速なキーボードと高速なCPUなど)を効率よく接続するために非常に重要な技術です。
この通信方式は、上位の分類である「電源とクロック」が提供する全体的なタイミング制御から独立して、データ自身にタイミング情報を含ませることで成立しています。具体的には、データブロックの先頭と末尾に目印(スタートビットとストップビット)を付加し、受信側がその都度タイミングを合わせる「調歩同期方式」を採用しているのが大きな特徴です。このようにして、共通のタイミング信号に縛られずに、柔軟で効率的なデータのやり取りを実現しているのです。
詳細解説
1. 階層における非同期通信の役割
私たちが今扱っている「コンピュータの構成要素」という大分類において、データの転送は欠かせません。しかし、コンピュータ内部のすべての部品が同じ速度、同じタイミングで動作しているわけではありません。「電源とクロック」が生み出すシステムクロックは、CPUやメモリといった主要な高速部品の動作を同期させる役割を担っていますが、周辺機器や外部インターフェースの速度はそれよりもはるかに遅いことが一般的です。
ここで、「同期とタイミング」の課題が浮上します。もしすべての通信を厳密なクロック同期(同期通信)で行おうとすると、低速なデバイスが高速なクロックに合わせる必要が生じ、システム全体がその遅いデバイスに引きずられてしまうか、あるいは高価で複雑なバッファリング機構が必要になってしまいます。
非同期通信は、この速度差の問題を解決するために生まれました。システム全体のクロックに依存するのではなく、データ自体が「いつ始まり、いつ終わるか」という独自のタイミング情報を持つことで、送信側がデータを送りたいときに送り、受信側がそれを受け取れるタイミングで処理できるようになるのです。これは、非常に賢い工夫だと感心しますね。
2. 動作原理:調歩同期方式
非同期通信の代表的な方式は「調歩同期方式(Start-Stop Synchronous)」と呼ばれます。この方式では、データ送信の最小単位(通常は1バイト、8ビット)ごとに、以下の特殊なビットを追加します。
-
スタートビット (Start Bit):
- データ送信が開始されることを受信側に知らせるための信号です。通常、通信線がアイドル状態(高電圧)から低電圧に変化した瞬間にスタートビットが認識されます。
- 受信側はこのスタートビットを検知した瞬間に、独自のタイミング(ボーレート:通信速度)でデータの読み取りを開始します。
-
データビット (Data Bits):
- 実際に送りたい情報(例:8ビット)です。
-
パリティビット (Parity Bit) ※オプション:
- データに誤りがないかを確認するための検査ビットです。
-
ストップビット (Stop Bit):
- データ送信が終了したことを示す信号です。通常は1ビットまたは2ビットの高電圧信号です。
- 受信側は、このストップビットによって次のスタートビットを待つ準備ができます。
このように、非同期通信では、1バイトのデータ本体の前後をスタートビットとストップビットで挟むため、データ本体よりも多くのビットを送信する必要があります。この余分なビットを「オーバーヘッド」と呼びますが、この小さな犠牲を払うことで、送信と受信のタイミングのずれを許容し、柔軟な通信を可能にしているのです。
3. 主要コンポーネント:UART
非同期通信を物理的に実現する主要な構成要素として、UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) があります。
UARTは、コンピュータ内部のパラレルデータ(複数のビットを同時に転送する形式)を、通信回線で扱うためのシリアルデータ(1ビットずつ順番に転送する形式)に変換し、逆にシリアルデータをパラレルデータに戻す役割を担っています。この変換過程で、スタートビットやストップビットの付加・除去、ボーレートの制御、そしてパリティチェックといった非同期通信に必要なすべての処理を行っています。
UARTは、まさに「コンピュータの構成要素」と外部世界をつなぐ、縁の下の力持ちのような存在だと言えますね。
具体例・活用シーン
非同期通信は、私たちが日常的に使う多くのデバイスで利用されています。特に、速度の保証が難しく、断続的にデータが流れる場面で真価を発揮します。
1. キーボードやマウスの入力
キーボードやマウスは、ユーザーが操作したタイミングでのみデータを発生させます。このデータ発生のタイミングは予測不可能で、システムクロックとは無関係です。非同期通信を使うことで、キーが押された瞬間にデータ(スタートビットからストップビットまで)を送り出し、CPU側はそれを随時受け取ることができます。もし同期通信を使っていたら、システムは常にキーボードからの入力を待ち続けなければならず、非常に非効率になってしまいます。
2. シリアルポート (RS-232C)
かつてPCの標準的なインターフェースであったRS-232C(シリアルポート)は、典型的な非同期通信の例です。プリンタやモデムなど、様々な周辺機器との接続に利用されていました。現在ではUSBに置き換わっていますが、組み込みシステムや産業用機器では、シンプルで信頼性が高い非同期シリアル通信は今でも現役で活躍しています。
3. アナロジー:郵便のやり取り
非同期通信を理解するための比喩として、郵便システムを考えてみましょう。
同期通信が「電話会議」だとすれば、非同期通信は「郵便」です。
- 電話会議(同期通信): 参加者全員が事前に時間を決め(共通クロック)、同時に参加する必要があります。誰かが話している間、他の人は聞く準備をしていなければなりません。タイミングが厳密です。
- 郵便(非同期通信): 手紙を送る側は、相手がいつ受け取れるかを気にせず、送りたいときにポストに投函します。手紙には必ず宛名(スタートビットのようなもの)と差出人(データの始まり)、そして封筒を閉じる(ストップビット)という明確な区切りがあります。受け取る側は、郵便物が届いたタイミングで自分のペースで開封し、内容を読みます。郵便配達のタイミングは一定ではありませんが、封筒という構造のおかげで、情報は正確に伝わるわけです。
この郵便のアナロジーからわかるように、非同期通信は、送信側と受信側がお互いの動作速度に縛られず、自由なタイミングでデータをやり取りできるという大きなメリットを持っているのです。
資格試験向けチェックポイント
非同期通信は、「コンピュータの構成要素」の動作原理、特に「同期とタイミング」に関する理解度を測る上で、IT資格試験で頻出するテーマです。特に同期通信との違いを理解しておくことが重要です。
| 試験レベル | 典型的な出題パターンと学習のヒント |
| :— | :— |
| ITパスポート | 定義とメリット:非同期通信とは何か、同期通信との主な違い(クロックの有無、柔軟性)を問う問題が出ます。「スタートビット」と「ストップビット」というキーワードが非同期通信を示す目印になることを覚えておきましょう。 |
| 基本情報技術者 | 動作原理とキーワード:「調歩同期方式」の仕組みを理解することが求められます。特に、スタートビット、データビット、ストップビットの役割と、データ転送効率(オーバーヘッド)に関する計算問題が出題されることがあります。また、非同期通信を実現するハードウェアとして「UART」の役割を問われることもあります。 |
| 応用情報技術者 | 応用と特性:非同期通信がどのような場面(例:低速な周辺機器との接続、通信速度が不安定なネットワーク)で適しているか、そのメリット・デメリットを深く理解する必要があります。また、同期通信(SDLC、HDLCなど)との効率や信頼性の比較を論述形式で問われることもあります。 |
覚えておくべき重要ポイント
- クロックの有無: 非同期通信は共通クロックを持たず、データ自身にタイミング情報(スタート/ストップビット)を含めます。
- オーバーヘッド: データ本体に加え、制御用のビット(スタート/ストップ)が必要なため、同期通信に比べてデータ転送効率がやや低下します。
- 用途: 速度差が大きい、またはデータ転送が断続的な構成要素間の通信に適しています。
関連用語
関連用語については、この文脈(コンピュータの構成要素 → 電源とクロック → 同期とタイミング)において、非同期通信の対となる概念、およびそれを実現する技術を中心に挙げるべきですが、現在提供されているインプット材料には具体的な関連用語のリストが不足しています。
- 情報不足: 非同期通信の理解を深めるためには、「同期通信(Synchronous Communication)」、「調歩同期方式(Start-Stop Synchronous)」、「UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)」、「ボーレート(Baud Rate)」、「クロック信号(Clock Signal)」といった用語との対比や関連付けが不可欠です。これらの用語を補完情報として追加することで、読者の理解が飛躍的に向上すると考えられます。