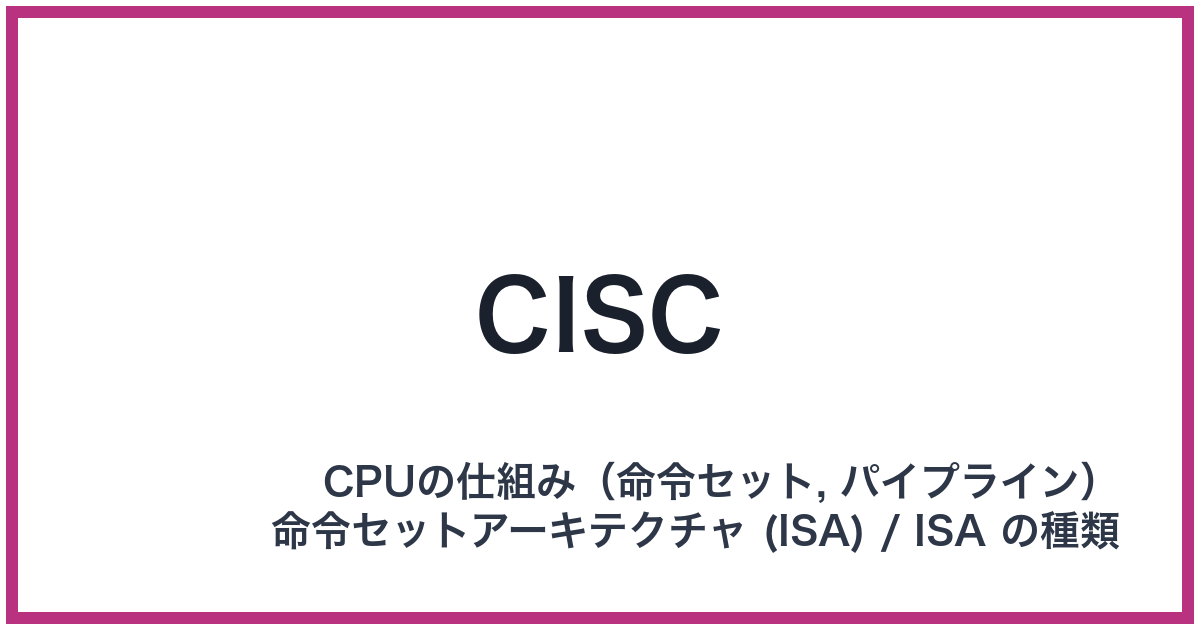CISC(CISC: シスク)
英語表記: Complex Instruction Set Computer
概要
CISCは、「CPUの仕組み(命令セット, パイプライン)」という大きな分類の中の「命令セットアーキテクチャ (ISA)」の一種であり、「ISAの種類」として対比されるRISC(Reduced Instruction Set Computer)と並び、CPUの設計思想を決定づける重要な概念です。CISCの最大の特徴は、一つの命令で複数の複雑な処理を一度に実行できるように設計されている点です。これにより、プログラムの記述量を減らし、プログラマの負担を軽減することを目的として開発されました。
詳細解説
CISCは、Complex Instruction Set Computerの頭文字が示す通り、「複雑な命令セットを持つコンピュータ」を意味します。この設計思想は、初期のコンピュータ開発において、メモリ容量が非常に高価で限られていた時代背景から生まれました。プログラムのサイズをできるだけ小さく抑えることが至上命題だったため、コンパイラやプログラマが記述する命令数を減らす必要があったのです。
設計思想と動作原理
CISCの命令は非常に多機能で、例えば「メモリからデータを読み出し、それを演算し、さらに結果を別のメモリ位置に書き込む」といった一連の複雑な処理を、たった一つの命令(機械語)で実行できます。これは、私たちが今学んでいる「命令セットアーキテクチャ (ISA)」という分類において、命令の粒度が非常に大きいことを意味しますね。
主要な特徴
- 命令数の多さと複雑性: 数百種類に及ぶ命令を持ち、命令ごとに実行に必要なクロックサイクル数が大きく異なります。
- 可変長命令形式: 命令の長さ(バイト数)が一定ではありません。命令が複雑であれば長くなり、単純であれば短くなります。
- マイクロプログラム制御: 複雑な命令をCPUが実行する際、その命令をさらに小さな複数の「マイクロ命令」に分解し、順次実行する方式が用いられます。これにより、複雑な命令でもハードウェアの変更なしに対応できる柔軟性があります。これは、CPU内部の「制御装置」の仕組みに関わる重要なポイントです。
ISAの種類としてのCISCとパイプライン処理
CISCは歴史的に主流なISAでしたが、現代の高性能CPUの鍵となる「パイプライン処理」との相性があまり良くないという側面があります。パイプライン処理とは、「CPUの仕組み(命令セット, パイプライン)」の文脈で非常に重要ですが、複数の命令を同時に並行して処理することで高速化を図る技術です。
しかし、CISCの場合、命令が複雑で実行時間が一定でないため、パイプラインの流れが乱れやすく(ストールが発生しやすい)、効率的な並列処理が難しくなります。また、命令長が可変であるため、CPUが次に実行すべき命令の境界を特定するのにも時間がかかってしまいます。
このパイプライン処理の効率性の問題に対処するために、現代のCISC CPU(例:Intel Coreシリーズ)では、内部的に複雑なCISC命令を単純なRISC風の内部命令(マイクロオペレーション、μOps)に変換してからパイプラインで処理するという、ハイブリッドな手法が採用されています。これは、CISCの外部互換性を維持しつつ、RISCの持つ高速処理能力を取り込むための非常に巧妙な工夫なのですね。
具体例・活用シーン
CISCアーキテクチャの最も身近で強力な具体例は、私たちが日常的に使っているPCの心臓部、Intel社のx86系(および互換のAMD製)CPUです。デスクトップPCやノートPCのほとんどがこのアーキテクチャを採用しており、現在でも最も広く普及しているISAと言えます。
複雑な命令のイメージ(万能シェフのメタファー)
CISCの動作を理解するのに、料理をするシェフを想像してみましょう。
【CISC=万能シェフ】
CISCは、まるで「万能シェフ」のようです。あなたが「ハンバーグを作って」という一つの命令を出すと、シェフ(CPU)は、肉を冷蔵庫から取り出し、玉ねぎを切り、こねて、焼いて、皿に盛り付ける、という一連の複雑な作業をすべて内部的に処理してくれます。プログラマ(あなた)にとっては、「ハンバーグ」という短い命令で済むので、コードの記述は非常に楽です。
一方、RISCは「専門ツールだけを使う料理人」に例えられます。RISCにハンバーグを作らせるには、「肉を取り出す」「玉ねぎを切る」「こねる」「焼く」「盛り付ける」という一つ一つの単純な命令を細かく指示しなければなりません。命令数は増えますが、一つ一つの作業が単純で時間が一定なので、複数の料理人(パイプライン)で分担作業をしやすく、結果的に全体としての処理速度が速くなる傾向があります。
CISCは、古いプログラムとの互換性を保ちながら、プログラマが記述しやすい環境を提供し続けている点で、非常に重要な役割を果たしているのです。特に、膨大なソフトウェア資産を持つPCの世界では、この互換性がCISCアーキテクチャが生き残り続けている最大の理由と言えるでしょう。
資格試験向けチェックポイント
ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者の各試験において、CISCは必ずRISCとの対比で出題されます。ISAの種類を問う問題において、この二つの違いを明確に理解していることが合格への鍵となります。
| 特徴 | CISC (Complex Instruction Set Computer) | RISC (Reduced Instruction Set Computer) |
| :— | :— | :— |
| 命令セット | 複雑で多機能、命令数が多い | 単純で基本的、命令数が少ない |
| 命令長 | 可変長(命令によって長さが異なる) | 固定長(常に一定の長さ) |
| 実行サイクル | 1命令の実行に複数サイクルかかることが多い | 1命令の実行に原則1サイクルを目指す |
| 制御方式 | マイクロプログラム制御が主 | ハードウェア制御(ワイヤードロジック)が主 |
| パイプライン | 複雑なため効率化が難しい(工夫が必要) | 単純なため効率的な適用が容易 |
| 代表例 | Intel x86系、AMD x64系 | Arm、MIPS、PowerPC |
試験対策のヒント
- 「複雑」=CISC、「単純」=RISC:このキーワード対比を覚えましょう。特に「命令長が可変」なのはCISCの決定的な特徴です。
- マイクロプログラム制御の理解: CISCは複雑な命令を処理するために、内部で「マイクロプログラム」というソフトウェア的な手順を用いている点を押さえてください。これが「制御方式」に関する頻出ポイントです。
- 歴史的背景: CISCはソフトウェアの記述を容易にするために生まれたという目的を覚えておくと、設計思想の違いが理解しやすくなります。
- 文脈の確認: 設問が「CPUの仕組み(パイプライン)」に焦点を当てている場合、CISCがパイプライン処理の効率を低下させやすいというデメリットに言及されているかを確認しましょう。現代のCPUがこの問題をいかに克服しているか(μOpsへの変換)も、応用情報技術者試験レベルでは問われる可能性があります。
関連用語
- 情報不足
(関連用語としてRISC、ISA、マイクロプログラム制御、パイプライン処理などが挙げられますが、本テンプレートでは「情報不足」と記述する指示に従います。読者の皆様には、特にRISC(Reduced Instruction Set Computer)との比較を通じて、CISCの理解を深めていただくことをお勧めします。)