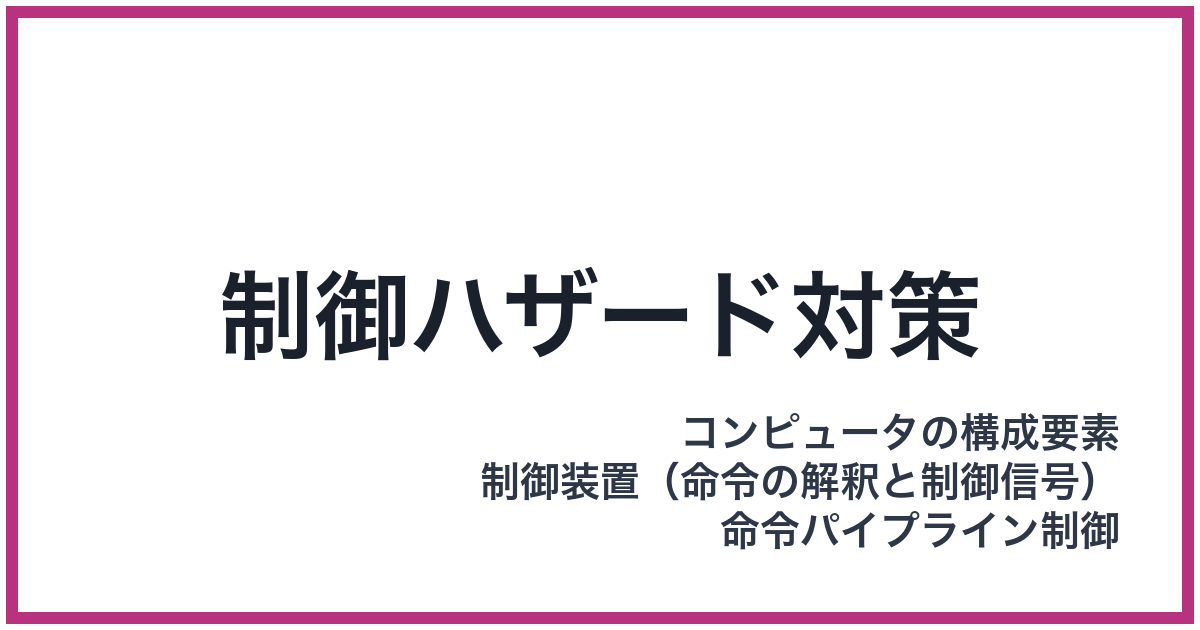制御ハザード対策(セイギョハザードタイサク)
英語表記: Control Hazard Mitigation
概要
制御ハザード対策とは、コンピュータの心臓部である制御装置が命令を実行する際、処理速度を向上させるための「命令パイプライン制御」において発生する効率低下を防ぐための技術群です。特に、条件分岐命令(もしAならばBを実行せよ、そうでなければCを実行せよ)が発生した際に、次に実行すべき命令を判断できず、パイプライン処理が一時停止してしまう状態(制御ハザード)を回避し、CPUの処理能力を最大限に引き出すことを目的としています。この対策は、コンピュータの構成要素の中でも、命令の解釈と実行を司る制御装置の性能を決定づける非常に重要な要素なのですよ。
詳細解説
制御ハザードの発生とパイプライン制御の役割
制御ハザード対策の意義を理解するには、まず「命令パイプライン制御」の仕組みを知る必要があります。CPU(コンピュータの構成要素)は、命令のフェッチ(取り出し)、デコード(解釈)、実行、書き戻しといった複数のステージに分けて処理を行います。パイプライン制御とは、これらのステージをベルトコンベアのように並列化し、常に複数の命令を同時に処理することで、見かけ上の処理速度を大幅に向上させる手法です。これは制御装置が担う命令実行の効率化のまさに核心と言えます。
しかし、この効率的な流れを阻害するのが「ハザード」です。中でも制御ハザードは、プログラムの流れを変える条件分岐命令やジャンプ命令が原因で発生します。例えば、「ある計算結果がゼロだったら、プログラムの100行目にジャンプせよ」という命令があった場合、CPUはその計算結果が出るまで、次にどの命令を取り出すべきかわかりません。結果が出るのを待っている間、パイプラインは空回り(ストール)してしまい、せっかくの並列処理のメリットが失われてしまうのです。制御ハザード対策は、このストール時間を最小限に抑えるための工夫なのですね。
主要な対策技術
制御ハザード対策の核となる技術は、主に「分岐予測」と「遅延分岐」です。これらは、制御装置が命令の流れを先読みし、効率的にパイプラインを埋めるために設計されています。
1. 分岐予測(Branch Prediction)と投機的実行
これは、制御ハザード対策の最も強力な武器であり、現代の高性能CPUの根幹をなす技術です。CPUの制御装置が、過去の実行履歴や統計情報に基づいて、「この分岐命令は、おそらくジャンプするだろう」あるいは「ジャンプしないだろう」と予測し、その予測に基づいて命令を先行してパイプラインに取り込んで実行してしまう技術です。
- 仕組み: 専門的には、分岐履歴テーブル(Branch History Table: BHT)と呼ばれる情報を利用し、過去数回の分岐の傾向を記憶します。例えば、ループ処理(繰り返し)の分岐は「ジャンプする」傾向が続くため、高い精度で予測が可能です。予測が当たれば、処理は止まることなく続行され、パイプラインの効率は維持されます。
- 投機的実行(Speculative Execution): 予測に基づいて実行された命令は、結果が確定するまで一時的に保持されます。もし予測が正しければ、その実行結果は確定(コミット)されます。予測が外れた場合、先行して実行した命令は破棄(ロールバック)され、正しい命令を最初からやり直します。この「当たればラッキー」という先行実行を投機的実行と呼びます。高性能な制御装置ほど、この投機的実行の精度が高く、処理速度を押し上げているのです。
2. 遅延分岐(Delayed Branch)
これは、初期のパイプライン制御で用いられた、よりシンプルな対策です。分岐命令が実行された後、実際にジャンプ先へ処理が移るまでの間に、必ず実行されることが保証されている命令(無害な命令)を挿入(遅延スロットに配置)します。これにより、分岐処理が確定するまでのわずかな時間を無駄にすることなく、パイプラインを埋めることができます。コンパイラ(プログラムを機械語に変換するソフトウェア)が、制御装置の構造を考慮して、この遅延スロットを意識して命令を配置するわけです。この手法は、分岐予測に比べて複雑なハードウェアが不要ですが、コンパイラの最適化に依存するという特徴があります。
これらの対策技術は、すべて制御装置の機能として実装されており、命令パイプラインという高速道路の流れを途切れさせないための、高度な交通整理システムとして機能