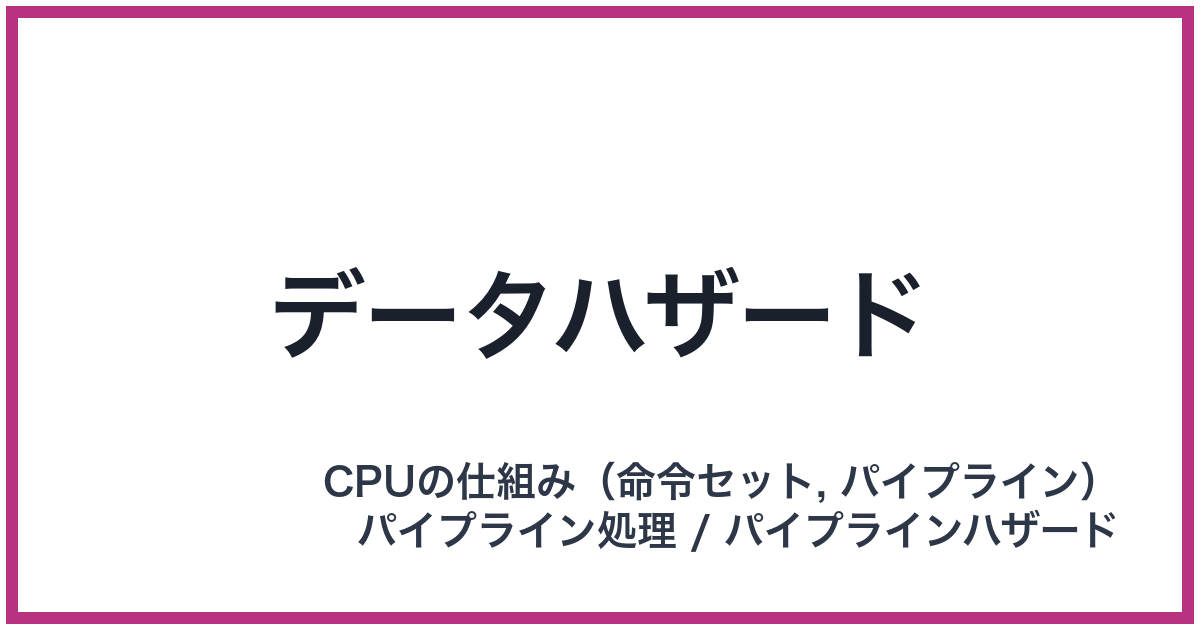データハザード
英語表記: Data Hazard
概要
データハザードは、CPUが高速処理のために採用しているパイプライン処理において、先行する命令の結果がまだ確定していないにもかかわらず、後続の命令がその結果を必要とする場合に発生する処理の矛盾です。これは命令間のデータの依存関係によって引き起こされます。このハザードが発生すると、CPUは処理の整合性を保つために、パイプラインの流れを一時的に停止(ストール)させる必要が生じます。この現象は、CPUの仕組み(命令セット, パイプライン)の効率を最大化する上で、克服すべき最大の課題の一つなのです。
詳細解説
データハザードを深く理解するためには、まずパイプライン処理の基本を思い出す必要があります。パイプライン処理とは、一つの命令の実行プロセスを複数の独立したステージ(例:命令の取り出し、解読、実行など)に分け、異なる命令を同時に異なるステージで処理することで、全体のスループットを向上させる技術です。これにより、見かけ上の命令実行速度(IPC: Instruction Per Cycle)が向上し、CPUの性能が劇的に改善しました。
しかし、この流れ作業が常にスムーズに進むわけではありません。命令Aの結果を使って命令Bを実行する場合、命令Aが結果を確定させる前に命令Bが実行ステージに進んでしまうと、命令Bは間違ったデータ(古いデータ、または未確定のデータ)を使って処理を進めてしまう危険性があります。これがデータハザードの核心です。
データハザードは、主に以下の3種類のデータの依存関係によって分類されます。
- RAW (Read After Write) 依存:
- 先行命令がレジスタにデータを書き込み (Write) 完了する前に、後続命令がそのレジスタからデータを読み込もう (Read) とするケースです。これが最も一般的で、結果の整合性を直接脅かすハザードです。
- WAW (Write After Write) 依存:
- 複数の命令が同じレジスタに書き込もうとし、パイプラインの構造が原因で、本来の命令順序とは逆の順序で書き込みが行われてしまうケースです。
- WAR (Write After Read) 依存:
- 先行命令がレジスタからデータを読み込み (Read) 終える前に、後続命令がそのレジスタに新しいデータを書き込んでしまう (Write) ケースです。
データハザードが発生した場合、パイプラインの整合性を守るために、後続の命令は必要なデータが利用可能になるまで待機しなければなりません。この待機サイクルを「ストール」と呼びます。ストールは、せっかくの並列処理のメリットを打ち消し、CPUの性能を低下させてしまいます。
解決策:フォワーディングの役割
この深刻な問題を解決するために、現代のCPUは「フォワーディング」(バイパシングとも呼ばれます)という高度な技術を採用しています。
フォワーディングの目的は、ストールを最小限に抑えることです。通常、命令の結果は最終的にレジスタファイルという記憶領域に書き込まれますが、フォワーディングでは、結果がレジスタに書き戻されるのを待たず、データが演算ユニット(ALU)などで生成された直後、つまりパイプラインの中間段階で、そのデータを必要とする後続命令のステージへ直接転送します。
この仕組みにより、先行命令がデータを完全に確定させるのを待つ必要がなくなり、パイプライン処理の流れが途切れることなく継続されます。フォワーディングは、データハザードを克服し、現代の高性能プロセッサの動作速度を支える、極めて重要な要素技術なのですよ。
具体例・活用シーン
データハザードがなぜ起こり、フォワーディングがどのように解決するのかを、日常の作業に例えて考えてみましょう。この理解は、CPUの仕組みを深く知るための第一歩です。
【料理のレシピと流れ作業のアナロジー】
あなたが非常に効率的な料理人であり、大きな料理を複数の工程(パイプラインステージ)に分けて作っていると想像してください。
- 命令1(先行命令): 「タマネギを切って炒める(結果R1を生成)」
- 命令2(後続命令): 「結果R1(炒めたタマネギ)を使って、ソースを作る」
データハザードの発生
あなたは焦って効率を上げようとしています。命令1がまだタマネギを切り終えていない(結果R1が未確定)にもかかわらず、命令2が「炒めたタマネギ」を要求してソース作りを始めようとしました。当然、命令2は必要な材料がないため、作業を中断せざるを得ません。
- 現象: 命令2の「材料待ち」が発生します。これがCPUにおける「ストール」です。
- 文脈: これは、命令1がデータを書き込む(Write)前に、命令2がデータを読み込もう(Read)とする、典型的なRAW依存のデータハザードです。
フォワーディングによる解決
ここで、フォワーディング(直接転送)の技術が登場します。
通常であれば、命令1は炒めたタマネギを一旦、冷蔵庫(レジスタファイル)に格納し、命令2が後で冷蔵庫から取り出す、という手順を踏みます。しかし、フォワーディングを採用すれば、命令1がタマネギを炒め終えた「瞬間」に、冷蔵庫を経由せず、すぐに命令2の作業台へ直接「はい、どうぞ!」