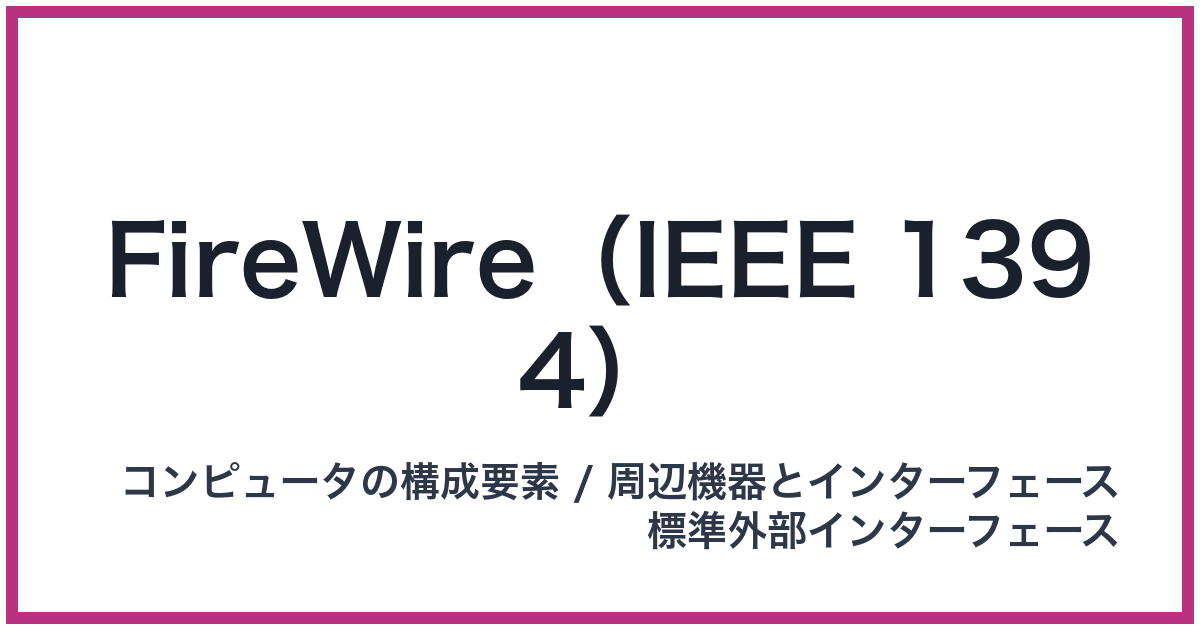FireWire(IEEE 1394)(IEEE: アイトリプルイー)
英語表記: FireWire (IEEE 1394)
概要
FireWire(ファイアワイヤ)は、コンピュータ本体と周辺機器を接続するためにかつて広く用いられた高速シリアルバス規格の一つです。これは「コンピュータの構成要素」における「周辺機器とインターフェース」の中でも、特にデジタルビデオカメラ(DVカメラ)やオーディオ機器といった高速かつ安定したデータ転送を必要とする機器を接続するための「標準外部インターフェース」として開発されました。Apple社が「FireWire」として、Sony社が「i.LINK」として採用を推進したことで知られており、大容量のデジタルデータ、特に映像データのリアルタイム転送に強みを持っていました。
詳細解説
FireWire(IEEE 1394)は、その名の通り、国際的な電気電子技術者協会であるIEEE(アイトリプルイー)によって標準化された技術規格です。この規格は、従来のパラレル転送方式(複数のビットを同時に送る方式)が抱えていた同期の難しさやケーブル長の制限を克服するため、シリアル転送方式(1ビットずつ順番に送る方式)を採用しています。これにより、ケーブルが細く、取り回しが容易になり、外部インターフェースとしての利便性が大幅に向上しました。
開発の背景と目的
FireWireが開発された主な目的は、デジタル化が進む映像・音響機器に対応するための高速インターフェースを提供することでした。特にDVカメラの普及期において、撮影した映像データを品質を落とさずにコンピュータに取り込み、編集作業を行うためには、当時の主流であったUSB 1.1では速度が不足していました。
FireWireは初期の規格(IEEE 1394a/FireWire 400)で最大400 Mbps、後の拡張規格(IEEE 1394b/FireWire 800)では最大800 Mbpsという高速転送を実現しました。これは、大容量のデジタルファイルを扱うプロフェッショナルやハイアマチュアにとって、周辺機器との接続を円滑にする上で非常に重要な要素でした。
アイソクロナス転送の採用
FireWireの最大の特徴であり、他の「標準外部インターフェース」と比較して優位性を持っていたのがアイソクロナス転送(Isochronous Transfer)のサポートです。
アイソクロナス転送とは、「一定時間ごとに決められた量のデータを保証して転送する方式」のことです。これは、映像や音声のように、データが途切れたり遅延したりすると致命的な問題となるリアルタイム性の高いストリーミングデータ転送に最適です。
例えば、ビデオカメラからPCへ映像を取り込む際、データ転送が一時的に停止したり遅れたりすると、映像がカクついたり、音が途切れたりしてしまいます。FireWireは、このアイソクロナス転送によって、まるで専用の高速バスのように、常に安定した帯域幅を確保し、スムーズなデータ転送を可能にしました。この技術こそが、FireWireが「周辺機器とインターフェース」の分野で、特にAV機器との接続において一時代を築いた理由です。
接続形態と特徴
FireWireは、デイジーチェーン接続(数珠つなぎ)やツリー状の接続形態に対応しており、最大63台までの周辺機器を接続できました。また、電源供給能力も持っていたため、一部の小型周辺機器はACアダプタなしで動作可能でした。さらに、コンピュータを介さずに機器同士を直接接続し、データ転送を行うピアツーピア接続が可能であった点も、柔軟な利用を可能にする優れた特徴でした。
この規格は、コンピュータと周辺機器を繋ぐための「標準外部インターフェース」として非常に高性能でしたが、後に登場したUSB 2.0やUSB 3.0が普及し、速度と汎用性の面で追い越されたため、徐々に市場での採用は減少していきました。
具体例・活用シーン
FireWire(IEEE 1394)が最も輝いていたのは、デジタルビデオ(DV)機器との接続シーンです。
1. デジタルビデオカメラ(DV)の接続
1990年代後半から2000年代にかけて普及した家庭用および業務用DVカメラは、FireWireポート(i.LINK端子)を搭載していることが標準でした。ユーザーはFireWireケーブルを使ってカメラとPCを接続し、撮影した映像をデジタル形式のまま、劣化させることなく高速で取り込むことができました。
【映像の高速道路というメタファー】
もしあなたが、非常に重要な生鮮食品(デジタル映像データ)を、生産地(DVカメラ)から消費地(PCの編集ソフトウェア)まで運ぶ任務を負ったと想像してください。当時のUSB 1.1は、データを運ぶための「一般道」のようなもので、速度制限があり、渋滞(遅延)も発生しやすかったのです。
しかし、FireWireは、この生鮮食品を鮮度(品質)そのままに、決められた時間内に確実に届けるための「映像専用の高速道路」のようなものでした。この高速道路(アイソクロナス転送)のおかげで、大量の映像データも途切れることなく、スムーズに目的地に到着し、すぐに編集作業に取り掛かることができたのです。
2. 高速外部ストレージ
FireWire 400やFireWire 800は、初期の高速外部HDD(ハードディスクドライブ)の接続にも使われました。特にMacintosh環境では、プロの映像編集者が大容量のデータを扱うために、SCSIに代わる高速インターフェースとして重宝されました。安定した帯域幅は、動画編集のように連続した読み書きが要求される作業に非常に適していたためです。
3. オーディオインターフェース
プロフェッショナル向けのオーディオインターフェース(マイクや楽器をPCに接続するための機器)にもFireWireは採用されました。これは、音楽制作においてレイテンシ(遅延)が非常に重要であり、FireWireのアイソクロナス転送が低遅延で多数のトラックの同時入出力を可能にしたからです。これもまた、周辺機器とインターフェースの接続において、リアルタイム処理の要求に応えるFireWireの優れた能力を示す例です。
資格試験向けチェックポイント
FireWire(IEEE 1394)は、ITパスポート試験や基本情報技術者試験、応用情報技術者試験において、コンピュータの「標準外部インターフェース」の歴史や特徴を問う文脈で出題される可能性があります。特にUSBとの違いを理解しておくことが重要です。
| チェックポイント | 詳細と試験対策の視点 |
| :— | :— |
| 正式名称と別名 | 正式名称は「IEEE 1394」です。Apple社による名称が「FireWire」、Sony社による名称が「i.LINK」であることを覚えておきましょう。 |
| 転送方式 | シリアル転送方式を採用していること。また、リアルタイム性の高いデータ転送を可能にするアイソクロナス転送をサポートしている点が最大の特徴であり、重点的に問われます。 |
| 速度規格 | 初期は400 Mbps (1394a)、後に800 Mbps (1394b) へと高速化されました。この数値は、USBの規格(USB 2.0の480 Mbpsなど)と比較して記憶しておくと良いでしょう。 |
| USBとの比較 | FireWireは主にデジタルAV機器(DVカメラなど)との接続に強く、USBは汎用性の高さと普及率で優位でした。FireWireは機器間のピアツーピア接続が可能である点も、USB 1.x/2.0との重要な違いです。 |
| 分類上の位置づけ | コンピュータと周辺機器を接続する「標準外部インターフェース」の一つとして、規格の歴史的な流れ(SCSI → FireWire/USB → Thunderbolt)の中で理解することが求められます。 |
関連用語
- 情報不足
(関連用語としては、競合するインターフェース規格である「USB(Universal Serial Bus)」や、FireWireの後継とも言える高速インターフェース「Thunderbolt(サンダーボルト)」、あるいはFireWireが代替した「SCSI(スカジー)」などが挙げられますが、具体的な情報提供がされていないため、ここでは情報不足とさせていただきます。)