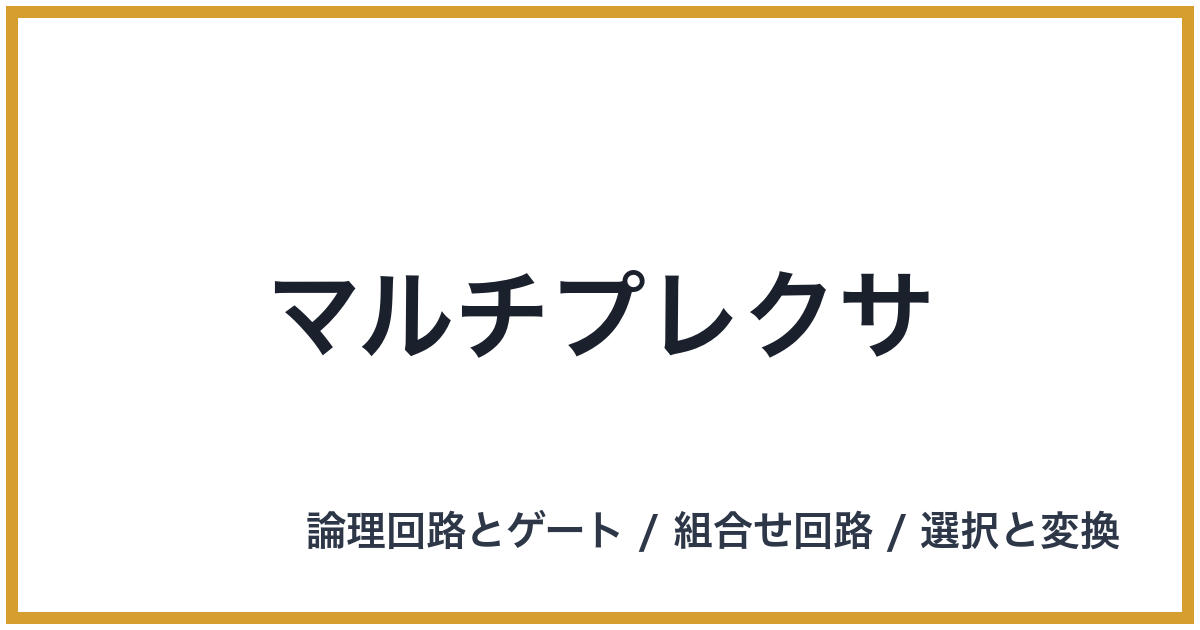マルチプレクサ
英語表記: Multiplexer
概要
マルチプレクサ(MUX)は、「論理回路とゲート」を構成する要素のうち、「組合せ回路」に分類される基本的なデジタル回路です。その役割は、複数のデータ入力信号の中から、選択入力(セレクタ)の指示に基づいて、ただ一つの信号を選び出し、それを単一の出力線へと導くことです。この機能は、デジタルシステムにおけるデータの流れを制御し、限られたリソース(出力線)を効率的に複数の情報源で共有するために不可欠であり、「選択と変換」というカテゴリの核心を担っています。例えるならば、多数の選択肢から一つを選ぶ、デジタル回路における非常に賢い「切替スイッチ」だと考えてください。
詳細解説
マルチプレクサが「論理回路とゲート」の体系の中でいかに重要であるか、そしてなぜそれが「選択と変換」という役割を担うのかを深く掘り下げてみましょう。
目的と構成要素
マルチプレクサの最大の目的は、時分割多重化(Time Division Multiplexing, TDM)など、限られた伝送路を複数のデータストリームで共有するために、入力データを切り替えることです。
この機能を実現するマルチプレクサは、主に以下の三つの重要な構成要素から成り立っています。
- データ入力線(Data Inputs): 実際に情報が流れてくる複数の入力ラインです($D_0, D_1, D_2, \dots$)。
- 選択入力線(Select Inputs / セレクタ): どのデータ入力を選択するかを決定する制御信号が入力されるラインです。この信号が回路の動作を完全に支配します。
- 単一出力線(Output): 選択されたデータが最終的に出力されるラインです。
動作原理:セレクタの支配力
マルチプレクサの動作原理は、選択入力線(セレクタ)の数とデータ入力線の数の関係に集約されます。セレクタが $N$ 本ある場合、その $N$ ビットで表現できる状態は $2^N$ 通りです。したがって、このマルチプレクサは最大 $2^N$ 本のデータ入力線を処理することができます。
例えば、4対1マルチプレクサ(4つのデータ入力、1つの出力)の場合、セレクタは2本必要です($2^2=4$)。この2本のセレクタ($S_1, S_0$)の組み合わせが、4つの入力($D_0$から$D_3$)のどれを出力 $Y$ に接続するかを決定します。
| $S_1$ | $S_0$ | 出力 $Y$ |
| :—: | :—: | :—: |
| 0 | 0 | $D_0$ |
| 0 | 1 | $D_1$ |
| 1 | 0 | $D_2$ |
| 1 | 1 | $D_3$ |
このように、セレクタの入力が変化すると、出力も即座に、遅延なく切り替わります。これは、マルチプレクサが記憶機能を持たない「組合せ回路」であることの明確な証拠です。入力信号の組み合わせによって、出力がただ一つに決まる、という組合せ回路の定義を忠実に守っているのですね。
論理回路としての実現とタキソノミー
マルチプレクサの選択機能は、ANDゲート、ORゲート、およびNOTゲートといった基本的な「論理回路とゲート」を組み合わせて実現されます。具体的には、セレクタの組み合わせ(積項)と対応するデータ入力をANDゲートで論理積をとり、その結果を全てORゲートで論理和をとることで出力が生成されます。
例えば、$D_0$が出力に選ばれるのは、「セレクタが00であり、かつ$D_0$が1である」ときです。これを論理式で表すと、$S_1′ S_0′ D_0$($S’$はNOTゲートを意味します)となります。すべての入力に対してこの論理和をとることで、マルチプレクサの機能が完成します。
この仕組みこそが、マルチプレクサが「選択と変換」カテゴリに属する理由です。複数のデータ入力という「多」の情報を、セレクタという制御信号に基づいて「一」の情報に選び出し、デジタル信号として最終出力へと変換しているからです。デジタル回路設計において、この選択的変換能力はデータのルーティングやプロセッサ設計において非常に重要な役割を果たしますのですよ。
具体例・活用シーン
マルチプレクサは、情報工学の様々な分野で、データの流れを整理し、効率化するために利用されています。特に初心者の方には、具体的な比喩を通じてその役割を理解していただきたいと思います。