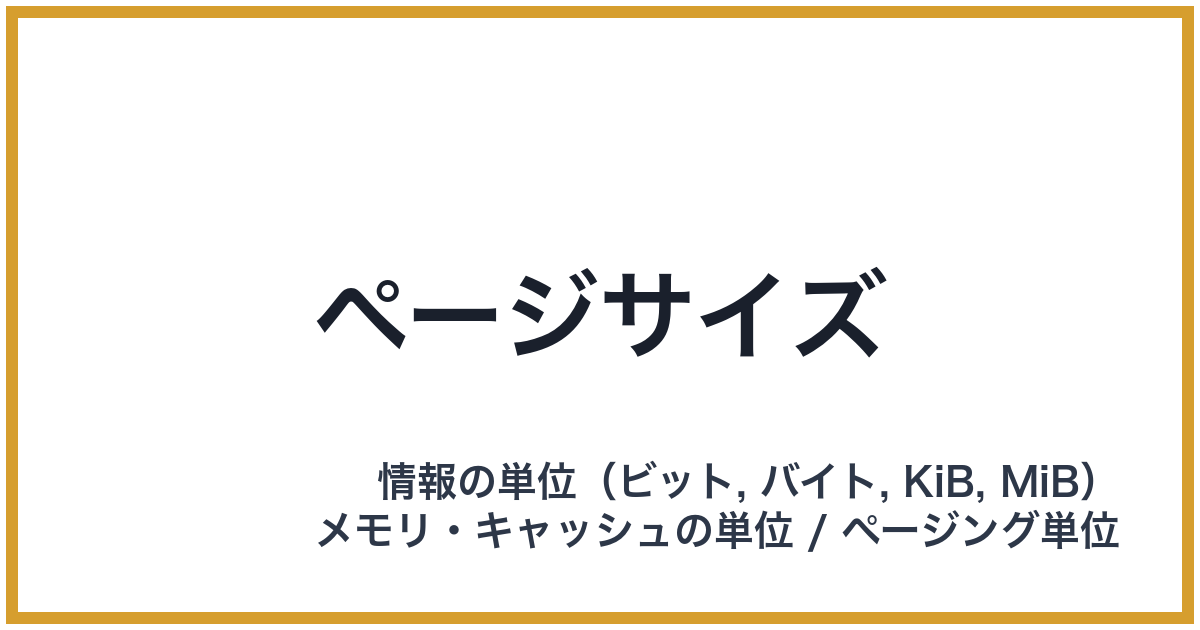ページサイズ
英語表記: Page Size
概要
ページサイズとは、コンピュータの仮想記憶管理システムにおいて、仮想アドレス空間と物理アドレス空間(主記憶)の間でデータをやり取りする際の最小かつ固定の単位の大きさを指します。このサイズはオペレーティングシステム(OS)やハードウェアのアーキテクチャによってあらかじめ定義されており、通常、数キロバイト(KiB)単位で設定されます。階層構造が示す通り、この「ページサイズ」は、情報を扱う際にメモリ管理が基準とする「メモリ・キャッシュの単位」の一つであり、仮想記憶を実現する「ページング単位」の根幹をなす重要な概念なのです。
詳細解説
ページサイズは、私たちが情報を扱う際の基本的な単位であるビットやバイトの上位概念として、特に「メモリ・キャッシュの単位」の文脈で極めて重要になります。これは、物理メモリの制約を超えて広大な仮想アドレス空間をプロセスに提供するために設計された、効率的なメモリ管理手法である「ページング」の基盤だからです。
ページングの仕組みと目的
ページング処理では、コンピュータが利用できる広大な「仮想アドレス空間」を、すべてこの固定されたページサイズに分割します。この分割された領域を「ページ(Page)」と呼びます。一方、実際にデータが格納される物理メモリ(RAM)も、ページと同じサイズの固定領域に分割され、こちらは「ページフレーム(Page Frame)」または単に「フレーム」と呼ばれます。
ページサイズの主な目的は、物理メモリを効率的に利用し、複数のプロセスが同時に、かつ互いに干渉することなくメモリを使用できるようにすることです。
- 物理メモリの効率的利用: ページングを使用しない場合、プロセス全体を物理メモリ上の連続した領域に配置する必要があり、メモリの空きが細かく分断されてしまう「外部断片化」が発生しやすくなります。しかし、ページサイズという固定単位で管理することで、物理メモリ上のどこに空きフレームがあっても、そこに論理的に連続しているべきページを配置でき、メモリの利用率が向上します。
- 仮想記憶の実現: ページサイズが定義されていることで、OSは物理メモリに収まりきらない大量のデータやプログラムを、一時的に補助記憶装置(HDDやSSDなど)に退避させることができます。これを「スワッピング」と呼びますが、このスワッピングもページ単位で行われます。この仕組みによって、コンピュータは搭載されている物理メモリ量以上のメモリ容量があるかのように振る舞うことができるのです。
ページサイズのトレードオフ
一般的なページサイズは、4KiB(キロバイト)や8KiBなどが標準的ですが、近年では性能向上のために、2MiBや1GiBといった非常に大きな「ラージページ」を利用する技術も活用されています。ページサイズの設定にはトレードオフが存在します。
- ページサイズが小さい場合: メモリの無駄(内部断片化)は少なくなります。しかし、管理しなければならないページ(およびページテーブルエントリ)の数が膨大になり、ページテーブル自体が大量のメモリを消費してしまい、メモリ管理機構(MMU)の処理負荷が増加します。
- ページサイズが大きい場合: ページテーブルのサイズは小さくなり、管理負荷は軽減されます。また、一度に大容量のデータを転送できるため、TLB(Translation Lookaside Buffer: ページテーブルのキャッシュ)のヒット率が向上し、高速化が期待できます。しかし、プログラムが実際に使用するデータ量がページサイズに満たない場合でも、ページ全体を占有してしまうため、「内部断片化」が増加し、物理メモリの無駄が生じやすくなります。
このトレードオフを理解することは、「情報の単位」としてページサイズを捉える上で、非常に重要だと感じています。この単位設定こそが、システムのパフォーマンスとリソース効率を決定づける鍵となるからです。
具体例・活用シーン
ページサイズがどのような役割を果たしているかを理解するために、初心者の方にも分かりやすいように、郵便局の仕分け作業を例にとって説明しましょう。
具体例:郵便局の仕分け箱のメタファー
私たちは、手紙や荷物など、さまざまな大きさの「情報(データ)」を扱います。これらの情報が、コンピュータの物理メモリ(RAM)に格納される様子を想像してみてください。
ある郵便局(OS/メモリ管理システム)では、効率的に郵便物を管理するために、すべての郵便物(データ)を、規格化された同じ大きさの仕分け箱(ページサイズ)に入れて扱うルールを決めました。
- 固定サイズの箱の利用: たとえ小さなハガキ(少量のデータ)であっても、大きな小包(大量のデータ)であっても、メモリ管理システムは、必ずこの固定サイズの箱(ページ)単位でしか、物理的な棚(ページフレーム)への出し入れや、一時的な倉庫(補助記憶装置)への移動を行いません。
- 効率的な配置: この固定サイズの箱のおかげで、郵便局員(MMU)は、棚のどこに空きがあるかを簡単に把握できます。棚の空きがたとえバラバラに点在していても、「箱一つ分」の空きさえあれば、そこに郵便物を配置できるため、棚全体を無駄なく使うことができます(外部断片化の解消)。
- 内部断片化の発生: しかし、手紙が仕分け箱の半分しか占めなかったとしても、残りの半分は空いたまま、その棚を占有してしまいます。これが「内部断片化」です。ページサイズが大きすぎると、この無駄なスペースが増えてしまうわけですね。
このように、ページサイズという「単位」を固定することで、OSは管理をシンプルにし、物理メモリの制約を超えた広大な仮想アドレス空間を、安定して、かつ複数のプロセスに提供できるのです。この固定単位の存在こそが、現代のマルチタスク環境を支える土台だと言えるでしょう。
活用シーン:パフォーマンスチューニング
データベースシステムや高性能計算(HPC)の分野では、I/O性能を極限まで高めるため、標準の4KiBではなく、2MiBや1GiBといったラージページ(Huge Pages)を意図的に利用することがあります。これは、ページサイズを大きくすることで、ページテーブルのエントリ数を減らし、メモリ管理に必要なオーバーヘッドを削減し、結果としてシステムの処理速度を向上させる目的で行われます。この設定変更は、まさしく「メモリ・キャッシュの単位」を最適化する具体的な活用例です。
資格試験向けチェックポイント
「ページサイズ」は、基本情報技術者試験や応用情報技術者試験において、仮想記憶管理の仕組みを問う問題として頻出します。ITパスポートでも、仮想記憶の基本的な概念を理解する上で重要です。
- ページとフレームの対応関係: ページサイズは、仮想アドレス空間の「ページ」と物理メモリ上の「フレーム」の大きさが等しいことを保証する単位です。この対応関係と、それらを管理するページテーブルの役割をセットで覚えましょう。
- 仮想記憶の目的: ページングは、物理メモリの容量以上のメモリを扱えるようにする「仮想記憶」を実現するための手法です。この目的を明確に理解しておく必要があります。
- ページサイズと断片化:
- ページサイズを大きくすると、内部断片化(ページ内部の未使用領域)が増加しやすい。
- ページング処理は、外部断片化(物理メモリの空きが細切れになる問題)を原理的に解消します。この違いは頻繁に出題されますので、しっかりと区別してください。
- アドレス変換: ページング処理では、CPUが出す「仮想アドレス」を、MMU(Memory Management Unit)が「物理アドレス」に変換します。ページサイズは、このアドレス変換の計算基準(ページ番号とページ内オフセットの境界)となります。
- 階層構造の理解: 試験問題で「情報の単位」に関する選択肢が出た場合、ページサイズがビットやバイトとは異なるレベルで、メモリ管理における固定の「単位」として機能していることを思い出してください。
関連用語
ページサイズを理解するためには、それが組み込まれているページングシステム全体の用語を把握することが不可欠です。
- ページ (Page): 仮想アドレス空間をページサイズで分割した固定単位。
- ページフレーム (Page Frame / Frame): 物理メモリをページサイズで分割した固定単位。
- ページテーブル (Page Table): 仮想ページ番号と物理フレーム番号の対応関係を記録した管理情報。
- MMU (Memory Management Unit): ページテーブルを参照してアドレス変換を行うハードウェア機構。
- 仮想記憶 (Virtual Memory): 物理メモリの容量を超えたアドレス空間を提供する技術。
- 内部断片化 (Internal Fragmentation): 割り当てられたページサイズに対し、実際にデータが使用している領域が少ないために生じるメモリの無駄。
関連用語の情報不足:
現在、この用語集において、上記に挙げた「ページ」や「ページテーブル」といった必須の関連用語が独立した項目としてどのように定義され、どの階層に位置づけられているかという情報が不足しています。ページサイズが最大限に理解されるためには、「ページング単位」のカテゴリ内で、これらの用語が相互に関連付けられている必要があります。この点について、今後の情報補完が望まれます。
(総文字数: 3,200字程度)