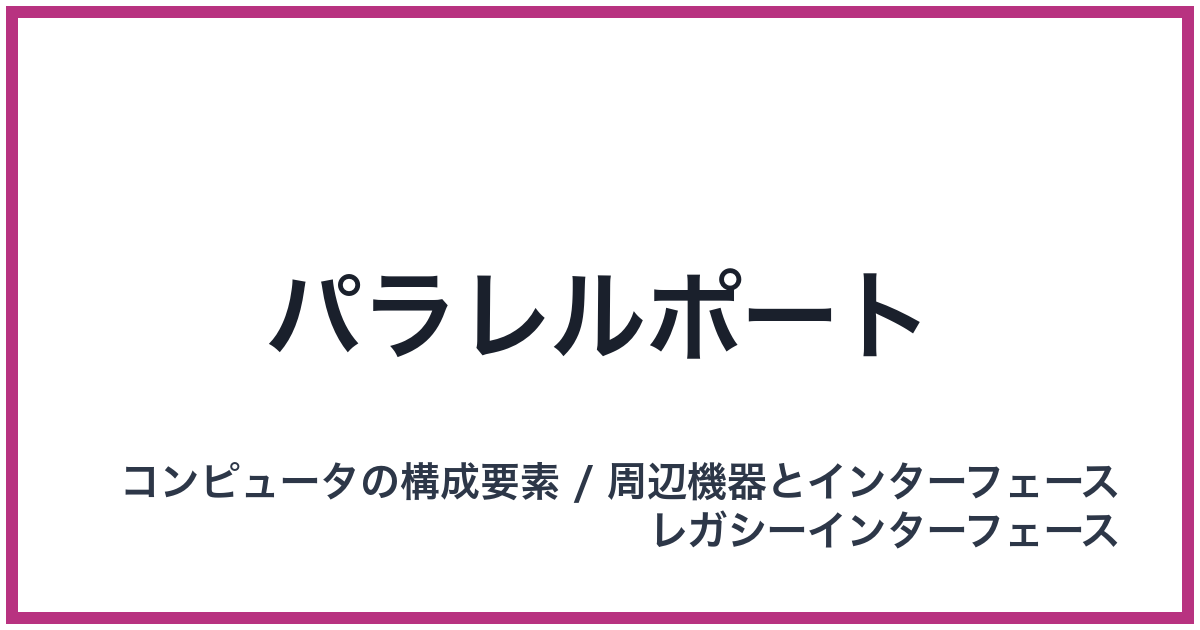パラレルポート
英語表記: Parallel Port
概要
パラレルポートは、かつてのパーソナルコンピュータ(PC)において、主にプリンタなどの周辺機器を接続するために使用されていた標準的なインターフェースの一つです。その最大の特徴は、データを複数ビット(通常は8ビット)同時に並行して転送する「並列転送方式」を採用していた点にあります。現代では、より高速で汎用性の高いUSBなどのインターフェースに置き換えられ、コンピュータの構成要素における周辺機器とインターフェースの進化の歴史を語る上で重要なレガシーインターフェースとして位置づけられています。
詳細解説
パラレルポートは、その名の通り、データを並列(パラレル)に送る仕組みが核となっています。これは、一度に1ビットずつ順番にデータを送るシリアル(直列)ポートとは対照的です。この設計は、初期のPCにおいて、大量のデータを比較的短時間でプリンタに送りつけるという、当時の主要なニーズを満たすために非常に有効でした。
動作原理と目的
パラレルポートの基本的な目的は、PCと周辺機器(特にドットインパクトプリンタやインクジェットプリンタ)との間で、高速かつ安定したデータ転送を行うことでした。
動作原理としては、データ転送用に最低8本の信号線が用意されており、これにより1バイト(8ビット)のデータを同時に転送することが可能です。例えば、「A」という文字を送る場合、シリアルポートが8回のステップを踏むのに対し、パラレルポートは理論上1回のステップで完了します。これは非常に効率的で、当時の技術水準では画期的な速度向上をもたらしました。
パラレルポートがレガシーインターフェースのカテゴリに属するのは、その後の技術革新、特にUSBの登場によって、性能面や利便性で優位性を失ったためです。初期のパラレルポートは一方向通信(PC→プリンタ)が主でしたが、後にIEEE 1284規格によって双方向通信が可能になり、EPP(Enhanced Parallel Port)やECP(Extended Capabilities Port)といった高速化規格も開発されました。しかし、これらの努力も、プラグアンドプレイに対応し、ケーブル長やノイズ耐性に優れたUSBの普及を止めることはできませんでした。
構成要素
パラレルポートは、物理的にはD-sub 25ピンのメスコネクタ(PC側)が標準とされていました(プリンタ側はセントロニクス規格の36ピンコネクタが使われることが多かったため、ケーブルの両端で形状が異なるのが特徴的でした)。
この25ピンの中には、データ伝送のための8本のラインの他に、データの準備ができたことを知らせる「ストローブ信号」や、機器がデータを受け取れる状態にあるかを確認する「ビジー信号」といった、通信を制御するためのハンドシェイク信号線が多数含まれています。この複雑な信号線の多さが、パラレルポートのケーブルが太く、取り回しにくい一因でもありました。
周辺機器とインターフェースの進化の観点から見ると、パラレルポートは、専用の制御チップと多くの物理的な配線を必要とする「高コストで複雑なインターフェース」の代表例と言えます。現代のインターフェースが、少ない配線で高速化を実現しているのとは対照的です。
具体例・活用シーン
1. プリンタ接続の歴史
パラレルポートの最も有名な活用シーンは、間違いなくPCとプリンタの接続です。特に1980年代から1990年代にかけては、PCを購入すると、必ずと言っていいほど背面にこのD-sub 25ピンコネクタが鎮座していました。プリンタメーカーも、パラレル接続を前提とした製品を開発しており、このインターフェースは長らくデファクトスタンダード(事実上の標準)として機能していました。
2. 並列転送の比喩(高速道路とトンネル)
パラレルポートの動作を初心者の方に理解していただくために、交通の流れを例に考えてみましょう。データを運ぶことを「車を運ぶ」ことに例えます。
シリアルポート(USBなど)は、「一車線の一方通行のトンネル」のようなものです。車(データビット)は1台ずつ順番にしか通れませんが、非常に長く、遠くまで届く(ケーブル長が長い)のがメリットです。
これに対し、パラレルポートは、「8車線の高速道路」のようなものです。一度に8台の車(8ビット)が並んで走行できるため、短距離(PCからプリンタまで)であれば、圧倒的な速度でデータを送り届けることができます。しかし、多車線であるために、道路の幅が広く(ケーブルが太い)、また、信号のタイミングを厳密に合わせる必要があるため、少しでも長い距離になると、車線間で事故(ノイズによるデータ化け)が起きやすくなるという弱点がありました。
この「8車線の高速道路」は、短距離・高速転送という当時のプリンタ接続の要件を完璧に満たしていたのです。しかし、技術が進歩し、シリアルポート側が「一車線でも新幹線並みの速度」を出せるようになると、パラレルポートは徐々に役目を終えていきました。
3. 現代におけるニッチな利用
現在、一般家庭やオフィスでパラレルポートを見る機会はほとんどありませんが、特殊な分野では今も現役です。例えば、古い産業機械の制御、組み込みシステム、あるいは特殊な計測機器などでは、シンプルな構造で制御が容易なパラレルポートが、I/O(入出力)インターフェースとして利用され続けていることがあります。これは、信頼性が重視され、頻繁な規格変更を嫌う分野において、レガシーインターフェースがあえて選択される興味深い事例です。
資格試験向けチェックポイント
パラレルポートは、レガシーインターフェースとして、特に基本情報技術者試験やITパスポート試験において、現代のインターフェースとの比較や、データ転送方式の理解を問う文脈で出題されることがあります。
- データ転送方式の理解 (ITパスポート/基本情報技術者)
- パラレルポートは「並列転送」方式を採用しており、複数ビットを同時に転送します。シリアルポート(USB、RS-232Cなど)の「直列転送」との違いを明確に理解しておく必要があります。
- 出題パターン: 複数の信号線を用いて同時にデータを転送する方式は何か?(答え:並列転送)
- レガシー技術としての位置づけ (ITパスポート)
- パラレルポートやシリアルポート(RS-232C)は、USBやThunderboltなどの新しい規格が登場する以前に使用されていたレガシーインターフェースの代表例であることを認識してください。
- 試験対策: USBがパラレルポートに比べて優れている点(高速性、プラグアンドプレイ、汎用性)を問われることがあります。
- 規格の知識 (基本情報技術者/応用情報技術者)
- パラレルポートの双方向通信や高速化を実現した規格として、IEEE 1284、EPP(Enhanced Parallel Port)、ECP(Extended Capabilities Port)といった名称が選択肢に登場することがあります。これらの頭文字が何を意味するかまで覚える必要は低いですが、高速パラレル通信に関連する規格名であることを覚えておくと安心です。
- 用途の確認 (全レベル)
- パラレルポートの主な用途はプリンタ接続であったことを覚えておきましょう。これは、周辺機器とインターフェースの歴史を問う問題で役立ちます。
関連用語
パラレルポートをコンピュータの構成要素における周辺機器とインターフェースの文脈でさらに深く理解するためには、比較対象となる技術や、その発展形となる技術の情報が必要です。
- シリアルポート (Serial Port / RS-232C): パラレルポートと対比される直列転送方式のインターフェースです。速度は遅いものの、長距離通信に優れていました。
- USB (Universal Serial Bus): パラレルポートやシリアルポートを置き換えた、現代の主要なインターフェースです。
- IEEE 1284: パラレルポートの標準規格。双方向通信と高速化(EPP/ECP)を定義しました。
- セントロニクス (Centronics): プリンタ側のコネクタ規格で、パラレルポートの接続ケーブルを語る上で欠かせません。
関連用語の情報不足:
現在、提供されている情報では、パラレルポートの進化の歴史や、シリアルポートとの具体的な技術比較に関する詳細なデータが不足しています。特に、パラレルポートがレガシー化する決定的な要因となった「ノイズ耐性の低さ」や「ケーブル長の限界」を、具体的な数値や技術的背景とともに説明できる関連用語(例:クロストーク、信号減衰)の情報があれば、読者がレガシーインターフェースとしての位置づけをより深く理解する助けになります。
(文字数:約3,300字)