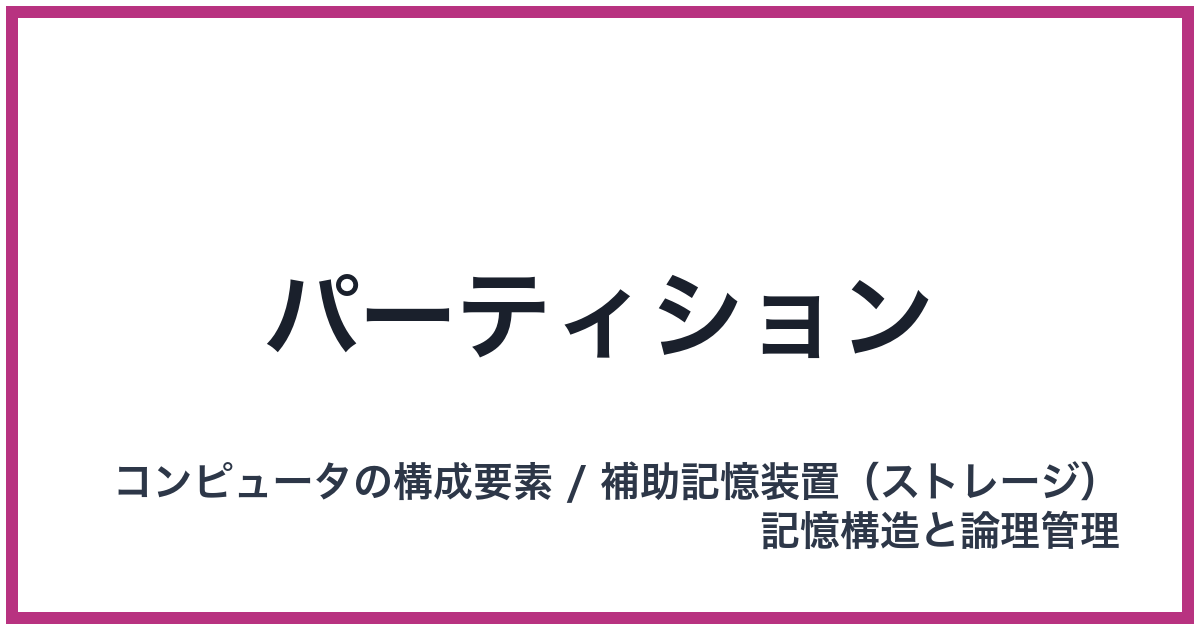パーティション(LVM: エルブイエム)
英語表記: Partition
概要
パーティションとは、ハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)といった物理的な補助記憶装置の記憶領域を、論理的に区切って管理するための仕組みです。このプロセスは、コンピュータの構成要素の中でも、特に補助記憶装置(ストレージ)の記憶構造と論理管理において、最も基礎的かつ重要なステップとなります。物理的な一つのストレージを複数の独立した区画に分割することで、それぞれの区画に異なるファイルシステムを適用したり、別々のオペレーティングシステム(OS)をインストールしたりすることが可能になるのです。
詳細解説
パーティションの目的は、物理的な制約からユーザーやシステムを解放し、柔軟なデータ管理を実現することにあります。ストレージは本来、ただの広大な記憶領域ですが、パーティションを設定することで、OSはその領域を論理的に分離された個別のドライブとして認識します。
記憶構造の基本と目的
パーティションは、ストレージを使用可能にするための最初のステップです。パーティションが存在しなければ、OSはどこからどこまでを管理対象として良いか判断できません。
- 分離と独立性: パーティションを分けることで、例えばOSのシステムファイル領域とユーザーのデータ領域を完全に分離できます。これにより、システム領域に問題が発生してもデータ領域への影響を最小限に抑えることが可能です。
- マルチブート環境の実現: 複数のOS(例:WindowsとLinux)を一つの物理ディスク上に共存させる場合、それぞれのOSが利用する領域をパーティションで明確に区切る必要があります。
- ファイルシステム適用前の準備: パーティションを作成した後、その区画に対して初めてフォーマット(ファイルシステムの設定)が行われます。パーティションは土地の境界線であり、フォーマットはその土地にどのようなルール(ファイルシステム)で家を建てるかを決める作業だと言えます。
パーティションテーブルの役割
パーティションの境界線や属性の情報は、ストレージの先頭部分に記録される「パーティションテーブル」によって管理されます。主要なパーティション管理方式には、以下の二つがあります。
- MBR (Master Boot Record): 従来の方式で、最大4つのプライマリパーティションを作成可能という制約や、管理できるディスクサイズが2TBまでという制限がありました。
- GPT (GUID Partition Table): MBRの制限を克服するために登場した新しい方式です。最大128個(OSによる)のパーティションを作成でき、事実上無制限のディスクサイズを管理できます。現在の標準的な方式です。
論理管理の進化:LVMの導入
従来のMBRやGPTによるパーティション管理は固定的な境界線に基づいていましたが、現代のIT環境、特にサーバーや仮想化環境では、より柔軟な「論理管理」が求められます。ここで登場するのが、Logical Volume Manager (LVM) です。
LVMは、従来の物理パーティション(またはディスク全体)を物理ボリューム (PV)として抽象化し、それらを束ねてボリュームグループ (VG)を作成します。そして、VGから必要なサイズを切り出して論理ボリューム (LV)としてOSに提供します。
LVMの最大の利点は、境界の柔軟性にあります。システム稼働中でも論理ボリュームのサイズを拡張・縮小したり、異なる物理ディスクにまたがって一つのボリュームを作成したりすることが可能です。これは、補助記憶装置の「論理管理」の概念を極限まで高めた技術であり、物理的な制約から完全に独立したストレージ運用を実現します。
具体例・活用シーン
パーティションの概念を理解することは、ストレージ管理の基礎を学ぶ上で非常に重要です。
アナロジー:巨大な倉庫の区画整理
パーティションを理解するための最も分かりやすい比喩は、「巨大な倉庫の区画整理」です。
想像してみてください。あなたは巨大な空の倉庫(これが物理的なストレージ全体、例えば10TBのHDD)を持っています。この倉庫に商品(データ)を収めたいのですが、もし区切りがないと、全ての商品がごちゃ混ぜになり、管理が非常に困難になります。
そこで、あなたは倉庫の内部を頑丈な壁で三つの区画に分けることにしました。
- 区画A(プライマリパーティション): システムOS専用の部屋。ここは絶対に触ってはいけない重要な場所です。
- 区画B(プライマリパーティション): 顧客データ専用の部屋。非常に厳重なセキュリティ(ファイルシステム)を敷きます。
- 区画C(拡張パーティション/論理ドライブ): バックアップや雑多なファイル用の部屋。
この壁で仕切られた区画一つ一つが「パーティション」です。各区画は完全に独立しているため、たとえ区画Aで火災(OSのクラッシュ)が発生したとしても、区画BやCのデータは安全に保たれる可能性が高まります。また、区画ごとに異なる管理者(異なるOSやファイルシステム)を割り当てることが可能です。
活用シーン
- データとシステムの分離: 多くの企業システムでは、OSが入っているCドライブとは別に、データ専用のDドライブを作成します。これはパーティションによる分離であり、OSの再インストールが必要になった際も、データ領域を保護できます。
- 仮想環境の基盤: サーバー仮想化技術(VMware, Hyper-Vなど)では、仮想マシン(VM)のディスクイメージを格納するために、物理ストレージ上に専用のパーティションやLVMの論理ボリュームを確保します。
- 暗号化の適用: 特定の機密データを含むパーティションのみにディスク暗号化(例:BitLocker, LUKS)を適用することで、セキュリティレベルを区画ごとに変える運用が可能です。
資格試験向けチェックポイント
ITパスポート、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験では、補助記憶装置の「記憶構造と論理管理」に関する知識が頻繁に問われます。特に、パーティションの基礎概念と、それを発展させたLVMの応用知識は重要です。
- MBRとGPTの比較:
- MBRの制約(2TB制限、プライマリパーティション4つまで)と、GPTがその制約をどう克服したか(大容量対応、パーティション数の増加)は頻出テーマです。
- 特に、ブート方式(BIOS/UEFI)とパーティション方式(MBR/GPT)の組み合わせに関する問題は、応用情報技術者試験でよく見られます。
- ストレージ利用の基本手順:
- 物理ディスクを利用可能にする手順「パーティション作成 → フォーマット(ファイルシステム構築) → マウント(OSが認識)」の流れは、基本情報技術者試験で知識が問われます。
- LVMの主要な構成要素(応用情報向け):
- LVMの階層構造(PV, VG, LV)とその役割を正確に理解しておく必要があります。
- PV (Physical Volume): 物理的なストレージ領域(ディスクまたはパーティション)。
- VG (Volume Group): PVを束ねた論理的なプール。
- LV (Logical Volume): 実際にOSがデータ領域として利用するボリューム。
- LVMが提供する柔軟性(オンラインでのサイズ変更、スナップショット機能など)が、従来のパーティション管理と比べて優れている点を説明できるようにしておきましょう。
- LVMの階層構造(PV, VG, LV)とその役割を正確に理解しておく必要があります。
- パーティションとファイルシステムの関係:
- パーティションはあくまで「区画」であり、実際にデータを読み書きするための「管理方法(ルール)」を提供するのがファイルシステム(NTFS, ext4など)であることを明確に区別して理解してください。
関連用語
- MBR (Master Boot Record)
- GPT (GUID Partition Table)
- ファイルシステム
- フォーマット
- LVM (Logical Volume Manager)
- 物理ボリューム (PV)
- ボリュームグループ (VG)
- 論理ボリューム (LV)
注記: 関連用語に関する詳細な説明は本記事のスコープ外であるため、情報不足とさせていただきます。それぞれの用語について、補助記憶装置の記憶構造における役割を個別に学習することをおすすめいたします。