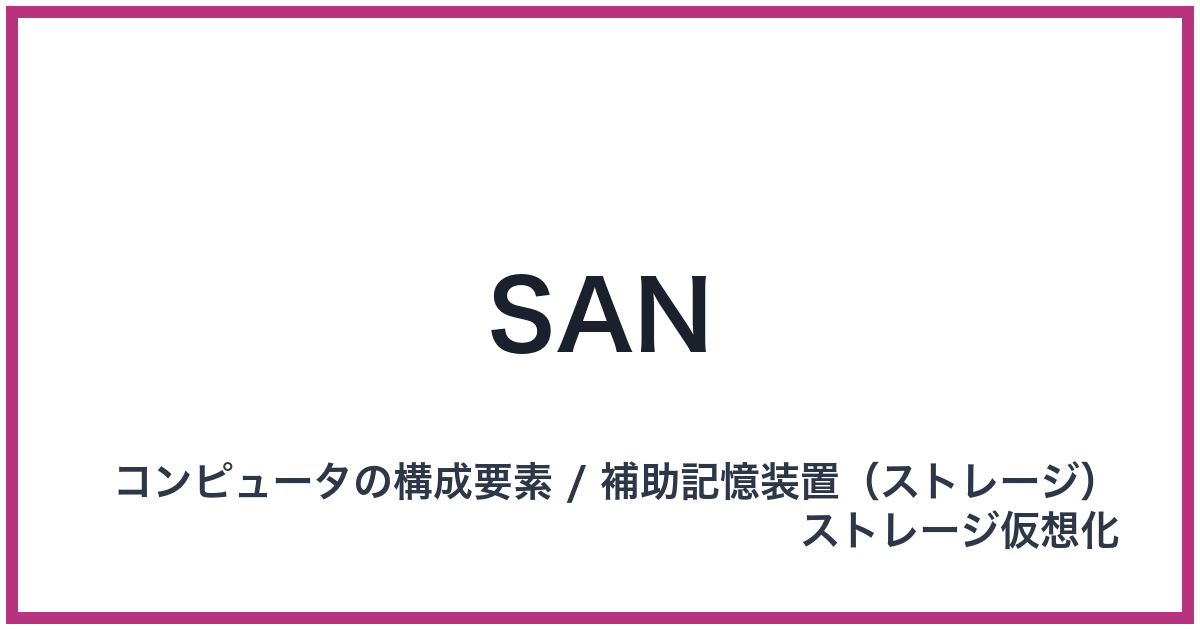SAN(サン)
英語表記: Storage Area Network
概要
SAN(Storage Area Network)は、複数のサーバーとストレージデバイスを高速な専用ネットワークで接続し、集中的に管理するための仕組みです。これは、従来のサーバーごとにストレージを持つ方式(DAS: Direct Attached Storage)の限界を超え、ストレージリソースをプール化(共有化)するために欠かせない技術です。コンピュータの構成要素の中でも補助記憶装置(ストレージ)の領域において、サーバーから見るとあたかも直接接続されているかのように振る舞いつつ、実際にはネットワーク経由でデータにアクセスすることを可能にします。
SANの最大の目的は、ストレージへのアクセス性能を確保しつつ、管理の効率化と高い可用性を実現することです。そして、この物理的な統合基盤こそが、次のステップであるストレージ仮想化を実現するための土台となるのです。
詳細解説
SANの必要性と目的
かつて、多くのシステムはサーバーとストレージが1対1で接続されるDAS方式を採用していました。しかし、システムが大規模化し、データ量が爆発的に増加するにつれて、DASでは以下の問題が顕在化しました。ストレージ容量の無駄、管理の複雑化、そして何より、あるサーバーのストレージが空いていても他のサーバーは利用できないという非効率性です。
SANはこれらの問題を解決するために登場しました。SANは、サーバー群とストレージアレイ群を、通常の業務ネットワーク(LAN)とは切り離された、専用の高速ネットワークで接続します。これにより、すべてのサーバーが共有されたストレージプールにアクセスできるようになります。
主要な構成要素と技術
SANを構成する主要なコンポーネントは以下の通りです。
- ホストバスアダプタ(HBA): サーバー側に搭載されるインターフェースカードで、サーバーをSANに接続する役割を果たします。
- SANスイッチ: ネットワークの中核を担い、サーバー(HBA)とストレージアレイ間のデータ通信を中継します。従来のLANスイッチとは異なり、ストレージプロトコル(主にFibre Channel)に特化しています。
- ストレージアレイ: 多数のディスクドライブを搭載し、RAIDなどの技術で冗長化された高性能な記憶装置群です。
- ケーブルとプロトコル:
- Fibre Channel (FC): 非常に高速で信頼性の高い通信を実現する、SANの伝統的なプロトコルです。高価ですが、ミッションクリティカルなシステムで広く利用されています。
- iSCSI (Internet Small Computer System Interface): 既存のイーサネットネットワーク(TCP/IP)上でSCSIコマンドをカプセル化して通信するプロトコルです。FCに比べて安価に構築できるため、近年普及が進んでいます。
ストレージ仮想化との深い関連性
SANは単なる接続技術ではなく、ストレージ仮想化を可能にする基盤として非常に重要です。
SANによって物理的にストレージが統合された後、管理者はこの巨大なストレージプールを論理的に分割し、個々のサーバーに割り当てます。この論理的な分割単位を「LUN(Logical Unit Number)」と呼びます。
例えば、物理的に100TBのストレージがあったとします。SAN環境では、これをサーバーAに20TB、サーバーBに30TB、そして残りを将来のバックアップ用に確保するといった具合に、柔軟にLUNとして切り出して提供できます。
このLUNの概念と、それをサーバーに提供する仕組みこそが、補助記憶装置(ストレージ)の文脈におけるストレージ仮想化の核心です。サーバー側から見ると、ネットワークの背後にある巨大なストレージアレイ全体が見えるわけではなく、割り当てられたLUNだけが、まるで自分のサーバーに直結されたハードディスクのように見えるのです。これは、物理的な制約から解放され、リソースの利用効率を劇的に高める、素晴らしい仕組みだと思います。
また、SANではLUNマスキングやゾーニングといった技術を使って、セキュリティを確保します。ゾーニングは、特定のサーバーと特定のストレージLUNだけが通信できるようにネットワーク経路を制限し、LUNマスキングは、サーバーに対して割り当てられたLUN以外は見せないようにする機能です。これにより、ストレージリソースを安全かつ柔軟に提供できるわけです。
具体例・活用シーン
比喩:専用の高速道路と集中型図書館
SANの仕組みを理解するための比喩として、「専用の高速道路と集中型図書館」のイメージが役立ちます。
通常のLANを「一般道」だとすると、SAN(特にFibre Channel SAN)は「ストレージ専用の高速道路」に例えられます。一般道では、メールやWebアクセスなど様々な交通が混在し、渋滞が発生しやすいですが、SAN高速道路はデータ転送(SCSIコマンド)だけのために使われるため、非常に高速かつ安定しています。
そして、この高速道路が接続しているのが「集中型図書館」であるストレージアレイです。かつては、各部署(サーバー)が小さな本棚(DAS)を持っており、それぞれ管理が大変でした。しかし、SANを導入することで、すべての本(データ)を巨大で安全な集中型図書館(ストレージアレイ)に集約できます。部署の職員(サーバー)は、必要なときに高速道路を使って図書館に行き、必要なデータ(LUN)だけを借りてくるイメージです。
この図書館の管理者が、職員ごとに借りられる本の範囲(LUN)を柔軟に調整してくれるのが、まさにストレージ仮想化の機能だと言えるでしょう。物理的な場所を意識することなく、必要な容量と高性能なアクセスを享受できるのです。
実際の活用シーン
- 大規模データベースシステム: データベースはI/O性能(データの読み書き速度)が非常に重要です。SANは高いスループットと低遅延を提供するため、金融機関や大規模ECサイトなどの基幹データベースのストレージ基盤として不可欠です。
- サーバー仮想化環境(VMware, Hyper-Vなど): サーバー仮想化では、多数の仮想マシン(VM)が同時に動作します。これらのVMのデータやOSイメージを一元管理し、高可用性(HA)やライブマイグレーション(稼働中のVMを別の物理サーバーに移動させる機能)を実現するためには、すべての物理サーバーが共有ストレージにアクセスできるSAN環境が必須となります。
- 災害復旧(DR)システム: SANは遠隔地のストレージアレイとデータを複製する(レプリケーション)機能と相性が良いため、重要なデータを地理的に離れた場所に安全に保管し、災害時にも迅速に復旧できる体制を構築できます。
これらの例からもわかるように、SANは単なる接続技術ではなく、現代のエンタープライズシステムにおける「高性能」「高可用性」「柔軟なデータ管理」を実現するための土台であり、ストレージ仮想化の実現には欠かせない要素なのです。
資格試験向けチェックポイント
IT関連の資格試験、特に基本情報技術者試験や応用情報技術者試験では、SANの基本的な概念と、類似技術との違いが頻繁に出題されます。SANが補助記憶装置(ストレージ)の文脈でどのように機能するのかを理解しておきましょう。
-
DAS、NAS、SANの区別:
- DAS (Direct Attached Storage): サーバーとストレージが1対1で直接接続される。共有機能がない。
- NAS (Network Attached Storage): ファイル単位(ファイルシステム)でネットワーク共有を行う。プロトコルはNFSやCIFS/SMB。主にLAN(イーサネット)を利用する。
- SAN (Storage Area Network): ブロック単位でアクセスするストレージ専用ネットワーク。サーバーからはローカルディスクのように見える。プロトコルはFCまたはiSCSI。
- ポイント: SANは「ブロックアクセス」である点が重要です。NASは「ファイルアクセス」であり、この違いが問われることが多いです。
-
主要技術の理解:
- Fibre Channel (FC): 高速・高信頼性だが高コスト。専用のHBAとスイッチが必要。
- iSCSI: 既存のTCP/IPネットワークを利用できるため、比較的安価にSANを構築可能。
-
ストレージ仮想化の要素:
- SANが物理的な統合基盤を提供し、その上でLUN(Logical Unit Number)をサーバーに割り当てることで論理的な分割(仮想化)が実現されることを理解してください。
- LUNマスキングやゾーニングといった、セキュリティとアクセス制御の仕組みも重要です。
-
出題傾向:
- 「サーバー仮想化環境において、仮想マシンのライブマイグレーションを可能にするために必要なストレージ構成は何か?」といった形式で、SANや共有ストレージの必要性を問う問題が出されます。SANは高可用性(HA)を実現するための必須技術として認識しておきましょう。
関連用語
- 情報不足
(注記: 本文中で触れたように、SANを理解するためには、Fibre Channel (FC)、iSCSI、NAS、LUN、ゾーニング、LUNマスキングなどの用語が関連しますが、テンプレートの制約に従い、ここでは「情報不足」と記載します。これらの用語を個別に学習することで、SANの理解がさらに深まることは間違いありません。)