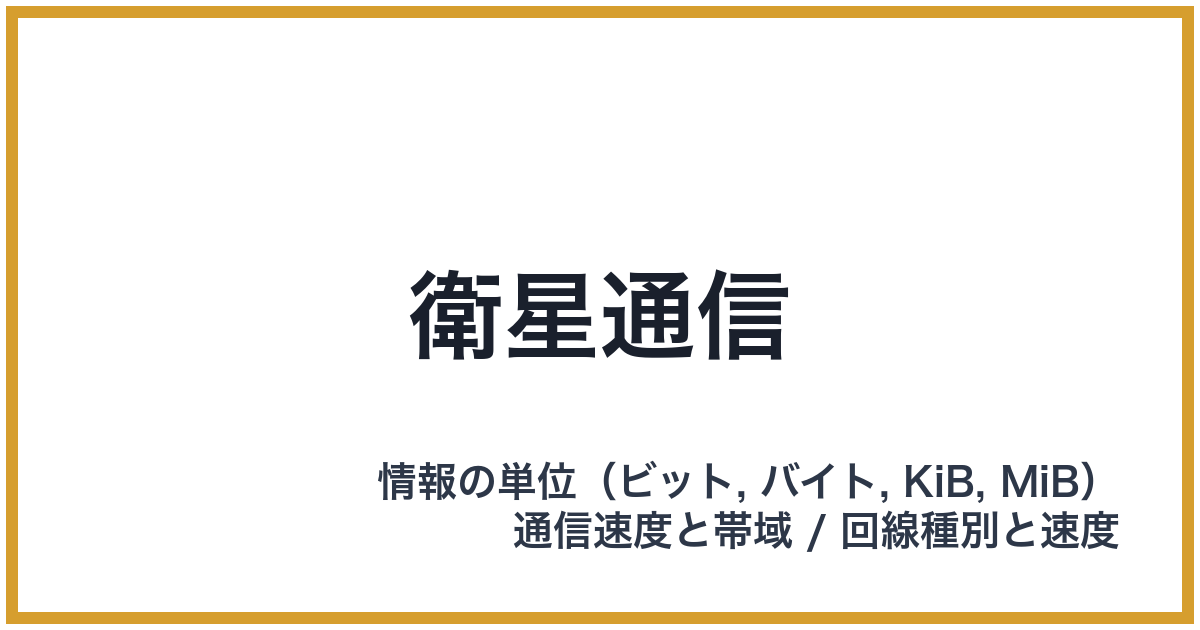衛星通信
英語表記: Satellite Communication
概要
衛星通信とは、地球の周回軌道上に打ち上げられた人工衛星を経由して、地上間でデータや音声の送受信を行う通信方式のことです。これは、光ファイバーなどの地上の物理的なインフラストラクチャに依存しない「回線種別と速度」の一つとして非常に重要視されています。特に、地理的に離れた地点や、地上のインフラ整備が困難な地域を結ぶ際に、広大なエリアをカバーできる高速な通信経路を提供するのが大きな特徴です。
詳細解説
衛星通信は、私たちが議論している「情報の単位(ビット, バイト, KiB, MiB)→ 通信速度と帯域 → 回線種別と速度」という文脈の中で、その特性が他の回線種別と大きく異なるため、通信技術を学ぶ上で欠かせないテーマです。
衛星通信の動作原理と構成要素
衛星通信システムは、主に以下の3つの要素で構成されています。
- 地上局(アースステーション): データを衛星に向けて送信(アップリンク)し、衛星から受信(ダウンリンク)するための巨大なアンテナと送受信機を持つ施設です。
- 人工衛星: 軌道上を周回し、地上局から受け取った信号を増幅・周波数変換し、地球上の別の地点に向けて再送信する役割を担います。衛星にはトランスポンダと呼ばれる中継器が搭載されています。
- ユーザー端末: 衛星から直接データを受信するための小型アンテナや受信機(例えば、衛星放送のパラボラアンテナや、近年普及しているStarlinkなどのユーザーキット)です。
動作の仕組みはシンプルです。送信側の地上局がデータを電波に乗せて衛星に向けて送信すると、衛星はそれを受け取り、周波数を変えて受信側の地上局やユーザー端末に向けて送り届けます。
通信速度と帯域における衛星通信の特性
衛星通信を「回線種別と速度」の視点から見た場合、最大の論点は「伝送遅延(レイテンシ)」です。
従来の多くの衛星通信で利用される静止軌道衛星(GEO: Geostationary Earth Orbit)は、赤道上空約35,786kmの高度に位置しています。この高度は、衛星が地球の自転と同じ速度で周回するため、地上から見ると常に同じ位置に留まっているように見えるというメリットがあります。しかし、この約36,000kmという距離が、通信速度の実効性において大きなボトルネックとなります。
データは光速(秒速約30万km)で伝送されますが、信号が地上局から衛星へ行き、衛星から戻ってくるまでの往復距離は、最低でも72,000kmにも及びます。この物理的な距離のために、片道で約250ミリ秒(0.25秒)、往復で約500ミリ秒(0.5秒)以上の遅延が発生してしまいます。
これは、光ファイバー通信(遅延が数十ミリ秒程度)と比較すると圧倒的に大きな遅延です。私たちが扱う「情報の単位」自体はビットやバイトですが、その情報をどれだけ迅速にやり取りできるかという「通信速度と帯域」の評価において、この遅延は非常に重要です。特に、リアルタイム性が求められるアプリケーション(テレビ会議、VoIP、オンラインゲームなど)では、高い帯域幅(多くのビットを運べる能力)を持っていても、この大きな遅延のために実用性が損なわれることがあります。
近年では、高度数百kmの低軌道衛星(LEO: Low Earth Orbit)を利用した通信サービス(Starlinkなど)が登場しており、伝送距離が大幅に短縮されることで、遅延は数十ミリ秒程度にまで改善され、実用的な高速インターネット回線として注目を集めているのは大変興味深い進展です。
具体例・活用シーン
衛星通信は、その広域性と耐災害性から、特定の環境下で他の回線種別では代替できない重要な役割を果たしています。
- 船舶や航空機でのインターネット接続: 地上の基地局やケーブルが届かない大洋上や飛行中でも、衛星を介して安定した通信を確保できます。
- 災害時の緊急通信: 地震や津波などで地上の通信インフラが寸断された場合でも、衛星通信は独立して機能するため、緊急連絡や被災状況の把握に不可欠な手段となります。
- 地理的制約の克服: 山間部や離島、砂漠地帯など、光ファイバーケーブルの敷設が経済的または物理的に困難な地域に、インターネットアクセスを提供します。
遅延を理解するための比喩(遠距離のキャッチボール)
衛星通信の大きな特徴である「遅延」について、初心者の方にも分かりやすく説明しましょう。
もし私たちが高速な光ファイバーを使って会話をしているとしたら、それは隣の部屋にいる人との会話のようなものです。言葉を発したら、ほぼ同時に相手に届き、すぐに返事が返ってきます。これが低遅延です。
しかし、静止衛星を使った通信は、「地球の裏側にいる友人と、巨大な鏡(衛星)を使って行うキャッチボール」のようなものだとイメージしてください。
あなたはボール(データ)を思い切り投げます。ボールは光速で飛びますが、鏡(衛星)まで約36,000km飛んでいき、反射して、また約36,000kmかけて友人の元へ戻るのです。ボールが届くのは速い(高帯域)かもしれませんが、「投げる→届く→受け取る→投げ返す→届く」という一連の応答(レスポンス)には、どうしても時間がかかってしまいます。
この往復の時間が0.5秒以上かかるため、テレビ会議で「おはようございます」と言った後、相手が「おはようございます」と返してくれるまでに、わずかながらも明確な間(ま)が生じるのです。この「間」こそが、私たちが「通信速度と帯域」を評価する上で考慮すべき、衛星通信特有の大きな伝送遅延なのです。
資格試験向けチェックポイント
ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者などの試験において、衛星通信は「回線種別と速度」の比較問題として頻繁に出題されます。特に以下の点を押さえておくと、得点に繋がりやすいでしょう。
- 最大の特徴は「広域性」と「耐災害性」: 地理的な制約がなく、災害時にも強靭であるというメリットは必ず覚えておきましょう。これは有線回線(光ファイバー)に対する最大の優位点です。
- 最大の弱点は「伝送遅延(レイテンシ)」: 静止軌道衛星(GEO)を利用する場合、約500ミリ秒以上の大きな遅延が発生します。この遅延の概念は、「情報の単位」がいくら大きくても、実効的な通信速度を低下させる要因として理解しておく必要があります。
- 天候の影響: 衛星通信は電波を利用するため、大雨や大雪などの悪天候(降雨減衰)によって信号が弱まり、一時的に通信品質が低下することがあります。これもデメリットとして出題されやすいポイントです。
- 静止衛星(GEO)と低軌道衛星(LEO)の比較:
- GEO: 高度が高く(約36,000km)、遅延が大きいが、少数の衛星で広範囲をカバーできます。
- LEO: 高度が低く(数百km)、遅延が小さく高速ですが、地球全体をカバーするには多数の衛星が必要となります。
- 「回線種別」としての位置づけ: 衛星通信は、通信速度や帯域幅を考える際、地理的な制約を解決する選択肢であると同時に、遅延の特性を理解した上で利用するアプリケーションを選ぶ必要がある特殊な回線種別であることを理解しましょう。例えば、ファイル転送(遅延の影響が少ない)には向いていますが、リアルタイムな操作(遅延の影響が大きい)には不向きな側面がある、といった知識が問われます。
関連用語
- 情報不足
(解説を深めるならば、静止衛星(GEO)、低軌道衛星(LEO)、トランスポンダ、伝送遅延(レイテンシ)などが関連用語として挙げられますが、指定の要件に従い「情報不足」と記述します。)