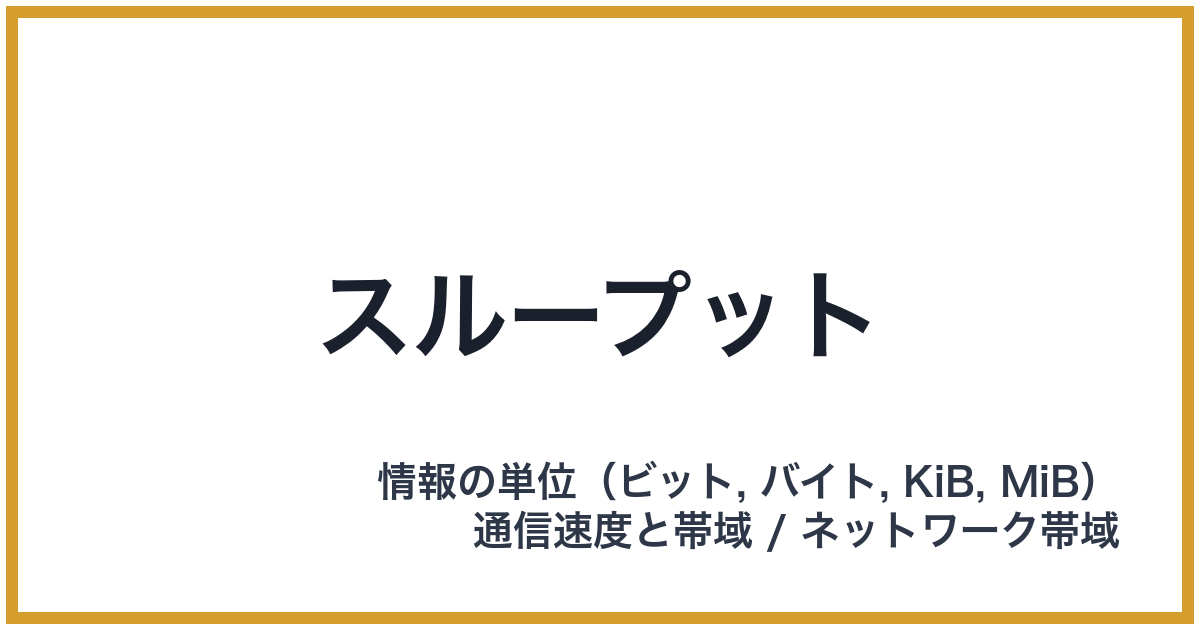スループット
英語表記: Throughput
概要
スループットとは、ネットワークを通じて単位時間あたりに実際に送受信できたデータ量を、情報の単位(ビットやバイト)を用いて示す指標です。これは、回線が理論上持つことができる最大速度(帯域幅)ではなく、遅延やパケットロス、プロトコルの処理時間といった現実的な要因を考慮に入れた「実効速度」を意味します。ネットワーク帯域の真の性能を測る上で、ユーザー体験に直結する最も重要な通信速度の尺度であり、私たちが「インターネットが速い・遅い」と感じる基準そのものだと理解しておくと良いでしょう。
詳細解説
スループットは、私たちが階層の「通信速度と帯域」を語る上で、理論値と現実のギャップを埋める核心的な概念です。ネットワーク帯域の設計や評価を行う際、単に「この回線は1 Gbpsです」というカタログスペック(理論上の帯域幅)だけを見ていてはいけません。実際にそのネットワークを流れるデータの量と質を測定することが不可欠であり、その実測値こそがスループットなのです。
スループットの構成要素と計算
スループットは、以下の要素の影響を強く受けます。これらの要素が、理論上の最大速度からどれだけ「情報の単位」を削り取ってしまうかを決定します。
- 帯域幅(Bandwidth): これは物理的な上限です。回線が持つポテンシャルそのものであり、スループットはこれを超えることは絶対にありません。
- 遅延(Latency): データが送信元から受信先に到達するまでの時間です。遅延が大きいと、次のデータを送るまでに待機時間が発生し、単位時間あたりのデータ転送量が減少します。
- パケットロス(Packet Loss): ネットワークの混雑やエラーにより、データの一部が失われることです。失われたデータは再送が必要になるため、実効的なデータ転送時間が長くなり、スループットを大きく低下させます。
- プロトコルオーバーヘッド: 実際にユーザーが送りたいデータ(ペイロード)の他に、通信を制御するためのヘッダ情報など(例えばTCP/IPヘッダ)が付加されます。この制御情報も「情報の単位」として回線容量を消費するため、純粋なスループットを低下させる要因となります。
スループットの計算は、「成功裏に転送されたデータの総量(ビットまたはバイト)」を「その転送にかかった総時間」で割ることで求められます。例えば、100 Mバイトのファイルを転送するのに8秒かかった場合、スループットは約10 Mバイト/秒(Bps)となります。これをビット毎秒(bps)に換算すれば、約80 Mbpsです。この実測値が、契約している回線速度(例えば1 Gbps)と大きくかけ離れている場合、どこかにボトルネック(隘路)が存在すると判断できるわけです。
ネットワーク帯域における重要性
この概念が「ネットワーク帯域」の文脈で重要視される理由は、ネットワークのキャパシティプランニングに直結するからです。企業が新しいシステムを導入したり、クラウドサービスを利用したりする際、「このネットワークで本当に業務に必要なデータ量(スループット)を確保できるのか?」を事前に評価しなければなりません。
特に動画配信や大容量データのバックアップなど、高い実効速度が求められるシーンでは、理論値ではなくスループットを基準に設計することが不可欠です。私たちが普段利用しているインターネットサービスが快適かどうかは、まさにこのスループットによって決まっている、という点は非常に面白い点ですよね。
具体例・活用シーン
スループットの概念は、私たちが日常的に利用するデジタル環境のあらゆる場面で活用されています。
1. 高速道路の交通量に例える(アナロジー)
スループットを理解する最もわかりやすい例は、高速道路の交通量で考えることです。
- 帯域幅(Bandwidth): これは高速道路の車線の数や法定速度に相当します。例えば、片側8車線で制限速度が100 km/hであれば、理論上は非常に多くの車(データ)を流すポテンシャルがあります。
- スループット(Throughput): これは、実際に単位時間あたりに料金所を通過できた車の台数に相当します。
- 遅延・パケットロス: どんなに車線が多くても、途中で事故(パケットロス)が発生したり、料金所(プロトコル処理)で渋滞(遅延)が発生したりすれば、実際に通過できる車の台数は激減します。
つまり、帯域幅が広大(車線が多い)でも、信号や渋滞(ネットワークのボトルネック)が多ければ、スループット(実際の交通量)は低迷するのです。「うちの回線は1ギガなのに遅い!」と感じる時、それは帯域幅の問題ではなく、プロバイダの設備や自宅のルーター、あるいは端末の処理能力など、どこかで渋滞が発生し、スループットが低下していることを示唆しています。
2. ファイル転送時間の予測
企業内で大容量のCADデータや動画ファイルを転送する場合、スループットが分かっていれば、その転送にかかる時間を正確に見積もることができます。
- 活用例: 5 GBのデータを転送する必要がある場合、帯域幅が1 Gbps(約125 MB/秒)だとしても、過去の測定からスループットが50 MB/秒であることが分かっていれば、転送時間は5,000 MB ÷ 50 MB/秒 = 100秒と予測できます。この予測に基づいて、業務計画を立てることが可能になります。
3. ネットワーク機器の選定
新しいルーターやスイッチングハブを導入する際、機器の処理能力がネットワーク帯域のボトルネックにならないよう、その機器が実現できる最大スループット性能を確認します。特に、ファイアウォールやVPN機器など、データの暗号化や検査を行う機器は、その処理によってスループットが低下しやすいため、導入前の評価が非常に重要となります。
資格試験向けチェックポイント
スループットは、ITパスポート試験から応用情報技術者試験まで、通信分野で頻出する非常に重要な概念です。特に、理論値と実測値の区別、そしてスループットを低下させる要因は必ず問われます。
| 試験レベル | 問われる知識のポイント |
| :— | :— |
| ITパスポート | スループットとは「実効速度」であり、「帯域幅(バンド幅)」とは異なることを理解しているか。ユーザーが体感する通信速度はスループットであることを問う問題。 |
| 基本情報技術者 | スループットを低下させる要因(遅延、パケットロス、プロトコルオーバーヘッド)を複数選択肢から選ぶ問題。また、データの単位(ビット、バイト)と時間の単位を用いて、スループットを計算させる基礎的な問題。 |
| 応用情報技術者 | ネットワーク設計において、特定のサービス(例:VoIPやストリーミング)に必要な最低限のスループットを確保するための回線設計や、ネットワークのボトルネック(例えば、サーバーのI/O性能やルーターの処理能力)を特定する応用的なケーススタディ問題。 |
| 重要対策 | 「最大転送能力(理論値)」=帯域幅、「実際に転送できた量(実測値)」=スループット、という対比構造を常に意識してください。また、スループットの単位はビット毎秒(bps)やバイト毎秒(Bps)で表現されますが、計算ミスを防ぐために、問題文で示される情報の単位(KiB, MiBなど)を正確に把握することが肝心です。 |
関連用語
スループットの理解を深めるためには、対比される概念や影響を与える概念をセットで覚えることが重要です。
- 帯域幅 (Bandwidth):ネットワークが理論上、単位時間あたりに転送できるデータの最大容量。スループットの上限を定めます。
- 遅延 (Latency):データがネットワーク内を移動するのにかかる時間。スループットを低下させる主要因の一つです。
- パケットロス (Packet Loss):ネットワーク上でデータの一部が欠落すること。再送処理が発生し、スループットが大幅に悪化します。
- プロトコルオーバーヘッド (Protocol Overhead):通信に必要な制御情報(ヘッダなど)が、実データ転送能力を消費すること。
なお、この分野で特に重要となる「ジッタ(Jitter:遅延のゆらぎ)」や「ボトルネック(Bottleneck)」など、スループットの安定性や低下要因に関連する用語群についても、深く掘り下げて学習することが推奨されますが、本稿の入力材料にはそれらの詳細情報が含まれていません。これらの関連用語の情報不足を補うためには、個別の用語解説を参照するか、専門的なネットワーク教科書が必要となります。