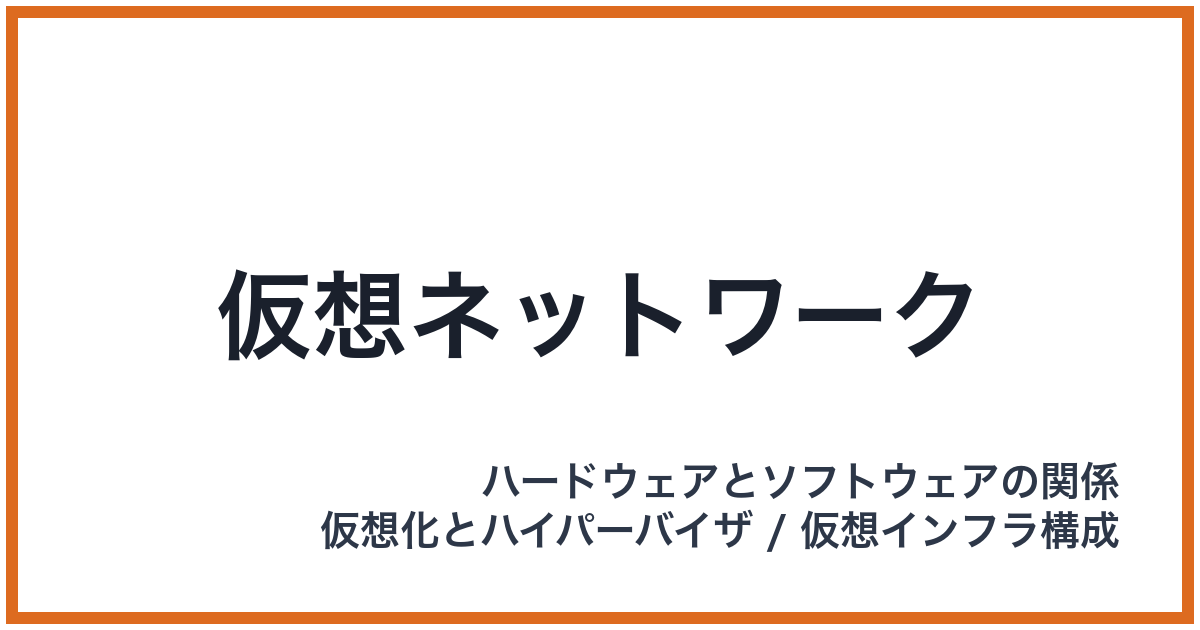仮想ネットワーク
英語表記: Virtual Network
概要
仮想ネットワークとは、物理的なネットワーク機器(ルーターやスイッチなど)に依存せず、ソフトウェアの力によって論理的に構築されるネットワーク環境のことです。これは、ハードウェアとソフトウェアの関係において、ソフトウェアがハードウェアの機能や配置を抽象化し、自由に制御可能にした成果の一つです。具体的には、仮想化とハイパーバイザ技術がサーバーを仮想化するのと同じように、ネットワークの機能そのものをソフトウェア的に実現し、利用者に提供します。これにより、物理的な制約から解放された、柔軟で迅速なネットワーク仮想インフラ構成が可能になります。
詳細解説
仮想ネットワークは、現代のデータセンターやクラウドコンピューティング環境において、必要不可欠な技術基盤です。この概念を理解するには、まず「なぜネットワークを仮想化する必要があるのか」という点、つまり、この概念が仮想インフラ構成の文脈でいかに重要かを知ることが大切です。
目的と背景
従来の物理ネットワークでは、サーバーを増設したり、部門ごとにネットワークを分離したりする際、物理的な配線変更や機器設定に多くの時間とコストがかかっていました。しかし、ハードウェアとソフトウェアの関係が進化し、仮想化技術が主流になるにつれて、サーバーやストレージは瞬時にプロビジョニングできるようになりました。ネットワークだけが物理的な制約に縛られたままでは、インフラ全体の柔軟性が損なわれてしまいます。
仮想ネットワークの主な目的は、このネットワーク設定のボトルネックを解消し、サーバー仮想化と連携してインフラ全体をソフトウェアで制御可能な状態(ソフトウェア定義型インフラストラクチャ、SDI)にすることです。
動作原理と主要コンポーネント
仮想ネットワークは、主に「オーバーレイネットワーク」技術と「ネットワーク仮想化」機能によって実現されます。
- オーバーレイネットワーク: 物理的なネットワーク(アンダーレイ)の上に、トンネル技術(例:VXLAN, NVGRE)を使って論理的なネットワーク(オーバーレイ)を構築します。このトンネルにより、仮想ネットワーク内の通信は、物理ネットワークをあたかも一本の大きなパイプのように利用し、その内部で論理的に分離された通信を実現します。これは、仮想化とハイパーバイザがCPUやメモリを抽象化するのと非常によく似た仕組みで、物理的な制約を隠蔽しているわけです。
- 仮想スイッチ(vSwitch): サーバー仮想化環境では、ハイパーバイザ(例:VMware ESXi, Hyper-V)が動作しています。このハイパーバイザ層に組み込まれた仮想スイッチが、仮想マシン(VM)間のトラフィックを処理し、外部の物理ネットワークへ接続する役割を担います。仮想スイッチは、物理スイッチと同じような機能(パケット転送、VLANタグ付けなど)をソフトウェア的に実行します。
- ネットワークコントローラー(SDN Controller): 複数の物理サーバー上の仮想ネットワークを一元管理するソフトウェアです。このコントローラーが、各仮想スイッチに対して設定情報(どの仮想マシンがどの仮想ネットワークに属するか、ルーティング情報など)を指示します。これにより、管理者はGUIやAPIを通じて、複雑な設定を自動化し、迅速に変更できるようになるのです。
これらのコンポーネントが連携することで、私たちは物理的な配線を気にすることなく、必要なIPアドレス帯やセキュリティポリシーを持つネットワークセグメントを、ソフトウェア定義で瞬時に作成し、仮想インフラ構成に組み込むことができるようになります。この柔軟性は、本当に画期的だと感じますね。
階層構造との結びつき
仮想ネットワークは、仮想化とハイパーバイザ技術がサーバーやストレージだけでなく、ネットワーク機能全体に適用された結果として存在します。この技術により、物理的な基盤(ハードウェアとソフトウェアの関係のハードウェア側)の上に、完全に論理的に分離された多数のネットワーク環境を同時に稼働させることが可能となり、最終的に高度に柔軟な仮想インフラ構成を実現するのです。もしネットワークが仮想化されていなければ、クラウドの柔軟性やスケーラビリティは実現できなかったでしょう。
(現在の文字数:約1,600文字)
具体例・活用シーン
仮想ネットワークの最も身近で具体的な例は、パブリッククラウドサービス(AWSのVPC、AzureのVNet、GCPのVPC Networkなど)で利用者が自由に構築できるプライベートなネットワーク環境です。
1. クラウドにおけるVPC (Virtual Private Cloud)
クラウド利用者が、自身のアカウント専用の隔離されたネットワーク空間を定義する際、まさに仮想ネットワークを利用しています。
- 活用シーン: 企業がクラウド上に本番環境と開発環境を構築する場合を考えてみましょう。物理的な世界であれば、ルーターやファイアウォールを別々に用意しなければなりません。しかし、VPCを使えば、ソフトウェア上で「本番用ネットワーク(10.0.1.0/24)」と「開発用ネットワーク(10.0.2.0/24)」を論理的に分離し、それぞれのネットワークに異なるセキュリティルール(サブネット、ルーティングテーブル、ネットワークACLなど)を適用できます。
2. 比喩による理解:バーチャルな高級マンション
仮想ネットワークの仕組みは、巨大な物理的な建物を、ソフトウェアによって高級でプライベートな「バーチャルマンション」として利用者に提供する様子に例えられます。
想像してみてください。巨大なデータセンターという「建物」が存在します。この建物の中には、物理的な配線やスイッチ(共有のインフラ)が張り巡らされています。
ここで、ある企業Aが「仮想ネットワーク」を構築するとします。これは、建物全体を仕切る巨大な壁ではなく、ソフトウェアが定義する目に見えない論理的な境界線です。
企業Aは、この境界線を使って自分専用の「フロア(仮想ネットワーク)」を作り、その中に「部屋(仮想マシン)」を配置します。企業Bも同じ建物の中にいますが、企業Aのフロアとは完全に隔離されており、お互いの部屋に勝手に入り込んだり、通信を傍受したりすることはできません。
これは、物理的な配線を変えることなく、建物全体のインフラ(ハードウェアとソフトウェアの関係におけるハードウェア)を共有しながら、各利用者が自分だけのプライベート空間(仮想インフラ構成)を迅速に手に入れることができる、魔法のような仕組みなのです。この柔軟性は、物理インフラを共有しつつ、高度なセキュリティとカスタマイズ性を提供する仮想化とハイパーバイザ技術の真骨頂と言えます。
(現在の文字数:約2,500文字)
資格試験向けチェックポイント
仮想ネットワークは、特に応用情報技術者試験や、基本情報技術者試験のネットワーク分野で頻出する、仮想インフラ構成の核となる概念です。以下の点を中心に学習してください。
- 仮想化技術との連動性: 仮想ネットワークは、サーバー仮想化(VM)とセットで出題されます。ハイパーバイザがVMを管理するように、ネットワーク仮想化技術(SDN、NFV)が仮想ネットワークを管理する、という構造を理解しておきましょう。これは、仮想化とハイパーバイザのセクションで深く学ぶべきポイントです。
- SDN (Software Defined Networking): 仮想ネットワークを実現するための技術の中心です。SDNは、ネットワークの制御(コントロールプレーン)とデータの転送(データプレーン)を分離し、制御を一元化する仕組みです。仮想ネットワークの柔軟性はこのSDNによって支えられています。
- NFV (Network Functions Virtualization): ルーター、ファイアウォール、ロードバランサといったネットワーク機能を、専用の物理機器ではなく、汎用サーバー上のソフトウェアとして実現する技術です。これにより、ネットワーク機能も迅速にプロビジョニング可能となり、仮想インフラ構成の完成度が高まります。
- オーバーレイネットワーク: 物理ネットワークの上に論理ネットワークを構築する仕組み(VXLANなど)の概念は、応用情報技術者試験で問われる可能性があります。「物理的な制約から解放される」という仮想化の基本原則と結びつけて理解してください。
- VLANとの違い: VLAN(Virtual LAN)も論理的なネットワーク分離技術ですが、物理スイッチの設定に依存し、拡張性に限界があります。仮想ネットワークは、ハードウェアとソフトウェアの関係において、物理的な制約を完全に抽象化し、より大規模で柔軟な分離を実現できる点がVLANとの決定的な違いです。
(現在の文字数:約3,000文字)
関連用語
仮想ネットワークは、仮想インフラ構成の重要な柱であり、多岐にわたる技術と密接に関わっています。本来であれば、SDN、NFV、VPC、ハイパーバイザ(Hypervisor)、仮想スイッチ(vSwitch)、オーバーレイネットワーク(Overlay Network)など、多くの技術用語を関連用語として挙げるべきです。
しかし、現時点ではそれらの技術用語に関する追加の文脈情報が提供されていません。
- 情報不足: 仮想ネットワークを支える具体的な技術である、SDN、NFV、VPCなどの用語定義に関する情報が不足しています。これらの用語を併せて解説することで、読者は仮想インフラ構成における仮想ネットワークの位置づけをより深く理解できるようになります。