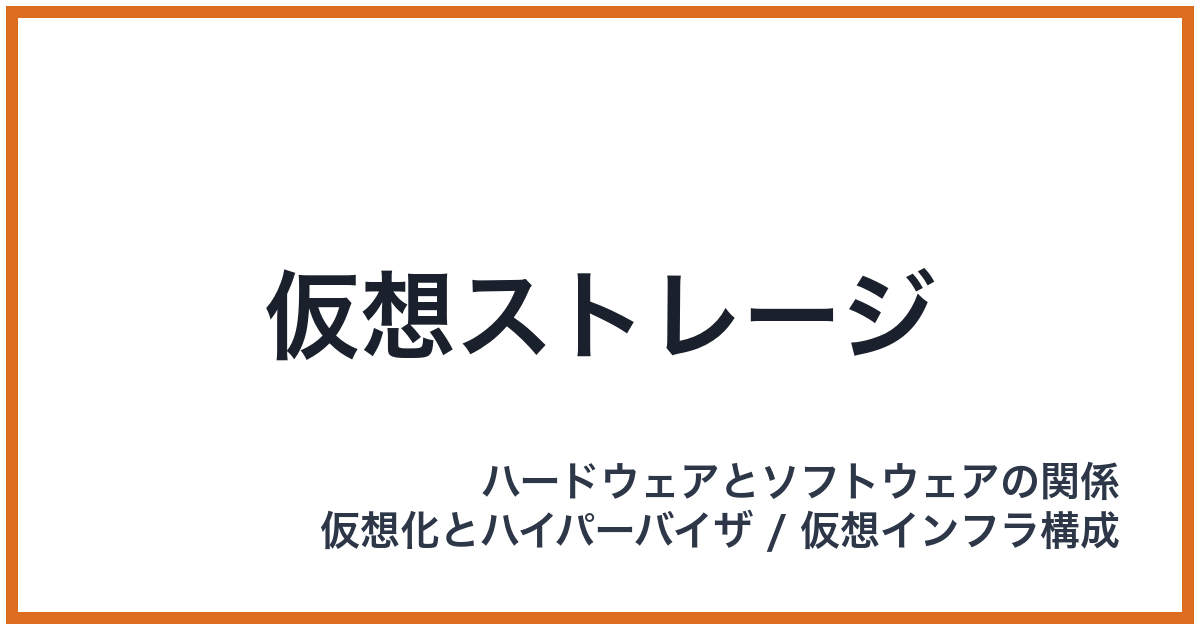仮想ストレージ
英語表記: Virtual Storage
概要
仮想ストレージとは、物理的に存在する複数のストレージデバイス(ハードディスクやSSDなど)をソフトウェアの力で統合・抽象化し、単一の大きなリソースプールとして扱う技術のことです。私たちが普段目にする仮想マシン(VM)に対して、物理的な場所や種類を意識させることなく、必要な容量や性能を柔軟に提供するために利用されます。これは、「ハードウェアとソフトウェアの関係」における「仮想化とハイパーバイザ」の領域で、サーバー仮想化と並んで「仮想インフラ構成」の三本柱(サーバー、ネットワーク、ストレージ)を支える、非常に重要な要素なのです。
詳細解説
仮想ストレージの目的と背景
仮想インフラ構成を考える上で、サーバーが仮想化されても、データが格納されるストレージが物理的に固定されていると、システム全体の柔軟性が損なわれてしまいます。例えば、あるサーバーのデータが必要になったとき、そのデータがどの物理ディスクのどこにあるのかを管理者が常に把握し、手動で移動させる必要が生じます。これでは、仮想化の恩恵である「リソースの流動性」を活かしきれません。
仮想ストレージの最大の目的は、この物理的な制約からの解放です。ソフトウェアのレイヤー(ストレージ仮想化ソフトウェアやハイパーバイザ機能の一部)が、さまざまな物理ストレージ(SAN、NAS、ローカルディスクなど)を統合し、それらを一つの大きな「ストレージプール」として論理的に管理します。
動作の仕組みと主要コンポーネント
仮想ストレージの仕組みは、物理的な実体と論理的な提供層を分離することにあります。
- 統合(プーリング): 異なるメーカーやスペックを持つ複数の物理ディスクをまとめて、ソフトウェア的に「ストレージプール」を作成します。このプールは、仮想化環境における総容量と総性能を表します。
- 抽象化: 仮想マシン(VM)は、物理的なストレージがどこにあるかを知る必要がなく、ただ「仮想ディスク」という論理的なファイルを受け取ります。VMから見ると、あたかも専用の物理ディスクが割り当てられているかのように見えます。
- プロビジョニング: 管理者は、このプールから必要な容量をVMに割り当てます。この際、「シン・プロビジョニング(Thin Provisioning)」という技術がよく使われます。これは、実際にデータが書き込まれた分だけ物理容量を消費し、必要に応じて容量を拡張できる機能で、ストレージの利用効率を飛躍的に高めることができます。
このように、仮想ストレージは、物理ハードウェアの複雑さをソフトウェアが吸収し、利用者(この場合は仮想マシンやアプリケーション)にシンプルで使いやすいインターフェースを提供するという、「ハードウェアとソフトウェアの関係」の理想的な形を実現していると言えるでしょう。特に「仮想インフラ構成」においては、この柔軟なストレージ管理が、システムの運用コスト削減と俊敏性の向上に直結します。
階層化と自動化
高度な仮想ストレージ環境では、「ストレージ階層化(Tiering)」も重要な機能です。これは、アクセス頻度の高いデータは高速なSSD(Tier 1)に、あまり使われないデータは安価で大容量のHDD(Tier 3)に、システムが自動的に配置し直す仕組みです。これにより、管理者が手動でデータを移動させる手間がなくなり、限られた予算の中で最適な性能を全ユーザーに提供できるようになります。これは、まさに「仮想化とハイパーバイザ」の文脈で求められる、リソースの最適化そのものなのです。
具体例・活用シーン
1. 企業におけるデータセンターの効率化
大規模なデータセンターでは、何百台ものサーバーと、それに接続される膨大なストレージが存在します。仮想ストレージを導入する前は、サーバーごとにストレージが固定され、あるサーバーでは容量が余っているのに、別のサーバーでは容量が不足しているという非効率が発生していました。
仮想ストレージを導入すると、すべての物理ストレージが統合されたプールとなり、必要なVMにリアルタイムで容量を割り当てたり、回収したりできます。これにより、ストレージの購入量を抑えつつ、利用効率を最大化できるようになります。これは、仮想インフラ構成の経済的メリットを最大限に引き出す活用シーンです。
2. 引っ越しが自由な図書館(メタファー)
仮想ストレージを理解するための具体的な比喩として、「引っ越しが自由な図書館」を想像してみてください。
従来の物理ストレージ環境は、固定された本棚(物理ディスク)を持つ図書館のようなものです。本(データ)を置く場所は最初から決まっており、本棚が満杯になったら、新しい本棚を物理的に追加し、司書(管理者)が手作業で本を移動させなければなりません。
一方、仮想ストレージは、巨大で柔軟な「魔法の書庫」です。司書は、どの物理的な本棚(SSDかHDDか)に本が置かれているかを気にしません。利用者が「この本が必要だ」とリクエストすると、システムが自動的に最適な場所から本を持ってきてくれます。さらに、利用頻度の高い本は、自動的に受付に近い高速な本棚(SSD)に移動され、めったに読まれない本は奥の倉庫(大容量HDD)に移動されます。
この「魔法の書庫」こそが仮想ストレージであり、管理者(司書)の作業負担を大幅に減らし、利用者に最高のサービス(性能)を提供するための仕組みなのです。
3. スナップショットとバックアップ
仮想ストレージの機能として非常に重要なのが「スナップショット」機能です。これは、ある時点の仮想ディスクの状態を瞬時に記録する機能で、システムに問題が発生した場合でも、すぐにその時点の状態に戻すことができます。これは、仮想インフラ構成におけるデータの保護と可用性を高める上で欠かせない機能です。
資格試験向けチェックポイント
仮想ストレージは、ITパスポートから応用情報技術者試験まで、幅広いレベルで問われるテーマです。特に「仮想化とハイパーバイザ」の文脈で、サーバー仮想化(VM)との連携が重要視されます。
| 試験レベル | 頻出する問われ方と対策 |
| :— | :— |
| ITパスポート試験 | 定義とメリットの理解。「物理的な制約を受けずにストレージを柔軟に管理する技術は何か?」といった形で、仮想ストレージの基本的な定義や、容量の効率的な利用(シン・プロビジョニングの概念)が問われます。 |
| 基本情報技術者試験 | 技術要素と用語の理解。仮想インフラ構成におけるサーバー、ネットワーク、ストレージの役割分担を理解しているかが問われます。特に「ストレージプール」「シン・プロビジョニング」「ストレージ階層化(Tiering)」といった専門用語の機能と目的を正確に把握しておく必要があります。 |
| 応用情報技術者試験 | 設計と運用の観点。仮想ストレージ環境を導入する際の性能設計(I/O性能のボトルネック回避)や、データ保護(RAIDと仮想ストレージの組み合わせ、スナップショットの運用)に関する高度な知識が問われます。また、クラウド環境(IaaS)におけるストレージサービスとの関連性も重要です。 |
| 共通の注意点 | 仮想ストレージが解決するのは「物理的なリソースの非効率性」であることを常に意識してください。また、サーバー仮想化(ハイパーバイザ)と仮想ストレージはセットで語られることが多いため、両者の連携を理解することが合格への近道です。 |
関連用語
- 情報不足
(関連用語として「ストレージプール」「シン・プロビジョニング」「SAN」「NAS」「ハイパーバイザ」などが挙げられますが、本インプットにはそれらの定義情報がないため、詳細な説明を省略します。)