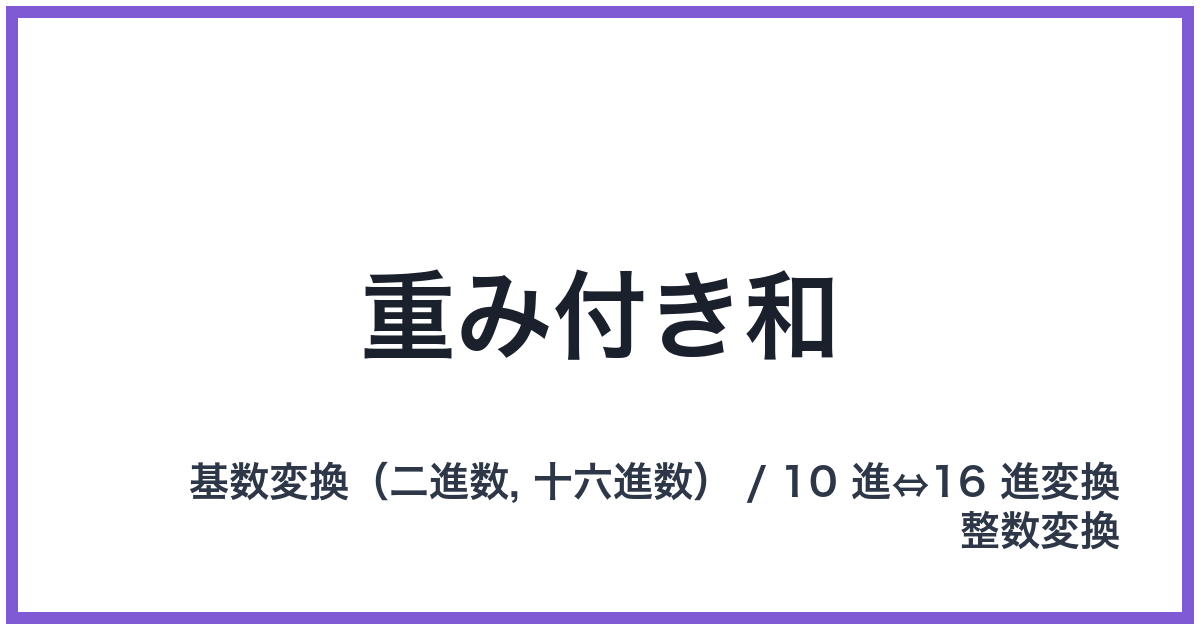重み付き和
英語表記: Weighted Sum
概要
重み付き和(Weighted Sum)とは、異なる基数(N進数)で表現された数値を、私たちが日常的に使用する10進数に変換する際に用いられる、もっとも基本的かつ重要な計算原理です。この手法は、変換対象の数の各桁の値に、その桁の位置が持つ「重み」(基数の冪乗)を乗算し、それらの結果をすべて合計することで10進数表現を導き出します。特に、この解説が位置する「基数変換(二進数, 十六進数) → 10 進⇔16 進変換 → 整数変換」という文脈では、16進数の整数を正確に10進数に直すための、核となる考え方として機能しています。
詳細解説
目的と階層内での役割
重み付き和の最大の目的は、コンピュータが効率的に扱うために採用している16進数や2進数といった記数法を、人間が直感的に理解できる10進数の価値に置き換えることです。
私たちが学んでいる「基数変換 → 10 進⇔16 進変換 → 整数変換」という流れにおいて、重み付き和は、16進数で表現されたメモリアドレスやレジスタ値を、具体的な数値として把握するために不可欠なプロセスです。例えば、メモリの容量やアドレスを16進数で見たとき、「それが具体的にいくつの値を示しているのか」を計算する際に、この重み付き和の原理が唯一の解答となります。
動作原理:位取り記数法の再認識
重み付き和を理解するためには、私たちが普段使っている10進数も、実は重み付き和で成り立っているという事実を再認識することが大切です。10進数の「427」は、無意識のうちに $4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0$ と計算されています。この $10^n$ の部分が「重み」です。
16進数から10進数への変換では、この基数を10から16に変えるだけです。したがって、16進数の各桁の重みは、右端(最下位桁、0桁目)から順に $16^0$ (1)、 $16^1$ (16)、 $16^2$ (256)、 $16^3$ (4096) と16の冪乗で増加していきます。
主要コンポーネント
重み付き和の計算を正確に行うために必要な要素は以下の通りです。
- 桁の値 (Digit Value):16進数の各桁に書かれている値です。ここで注意が必要なのは、16進数では「